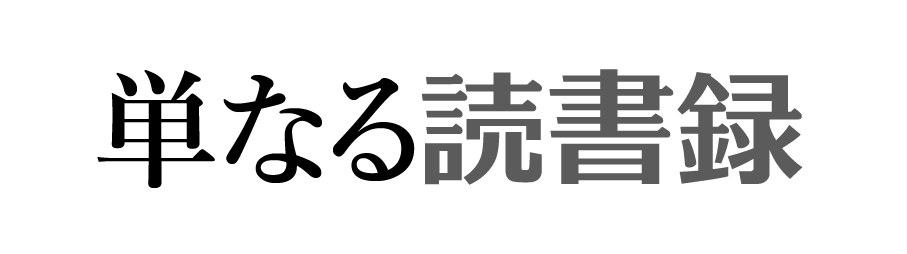僕がいま注目しているのは、遠く離れたレバノンの食糧危機。
一見、遠い国の話のように思えるこの危機が、実は日本にも迫っているように感じてならない。
レバノンで起きている食糧危機は、単純な経済問題ではない。
周辺国の紛争など、複合的な要因が絡み合い、国民の生活を根底から揺るがしている。
経済の崩壊、急激なインフレ、そして地政学的リスクが社会を侵食した。
有名な2020年のベイルート港大爆発は、まるでその危機に油を注ぐかのようだった。
爆発によって食糧貯蔵施設を喪失。
国の食糧供給能力を直撃した。
上記の複雑な要因とあわせて、いまや国民の約30%が深刻な食糧不足に苦しんでいる。
NHKのドキュメンタリー「2030未来への分岐点」が伝えるとある家族の物語は、その現実をリアルに映し出していた。
かつては安定した中流層以上の生活を送っていた彼らが、今や食料支援を求めるほどの窮状に陥っている。
あたりまえの日常が、文字通り一瞬にして崩壊してしまったのだ。
僕ら日本人も、楽観できる状況からは程遠い。
島国である日本の地理的特性は、大きな脆弱性を秘めているのは周知のとおりだろう。
海路や空路が遮断されれば、たちまち物資供給は困難となる。
特に農業分野での海外依存構造は、その脆弱性をことさらに浮き彫りにしている。
例えば、窒素肥料の主要成分である尿素の約90%が輸入に頼っているとことは、日本の農業生産力の未来に暗い影を落としている。
グローバル経済の歯車から外れれば、僕らの食卓は即座に危機に晒される。
主要肥料の輸入が滞れば、いまの生産力をもはや保つことはできないだろう。
さらに追い打ちをかけるのが、国際農産物市場の冷徹な現実だ。
中国の農産物市場の動向は、日本の食糧事情をさらに複雑にしている。
原発汚染水の問題が解決すれば、海産物の次は農産物の輸出拡大…というハナシになるだろう。
資本主義社会では当然のように、より高価格で買い取る海外市場に農産物は流れていく。
その結果、我ら庶民の主食であるコメの価格は確実に上昇の一途をたどるだろう。
政府の備蓄米放出策も、根本的な解決策とは言い難い。
5年間の保存期間のうち一部を放出し、さらにその分を1年以内に戻す仕組みは、実質的には現在の収穫分を前借りしているに過ぎない。
一時しのぎの対症療法に終始しているとしか言いようがない。
僕が言いたいのは、今の食料価格こそが「正常」だということだ。
コメだけでなく、キャベツ、トマト、卵、牛乳、パンなど、あらゆる食料の現在の価格が、実は私たちの経済の実態を正確に反映している。
これは単純に日本が貧しくなっていく過程が、食料価格に如実に表れているということにほかならない。
ここでは多くを書かないが、政治家の怠慢、優先順位の誤りと先送り、人気取りの政策。
レバノンが食糧危機から脱せないのは、こうした政治状況もあるという。
これらが国の根幹を揺るがし、未来への展望を曇らせている。
あぁ、似ている…と感じたのだ。
レバノンの危機は、決して遠い国の出来事ではない。