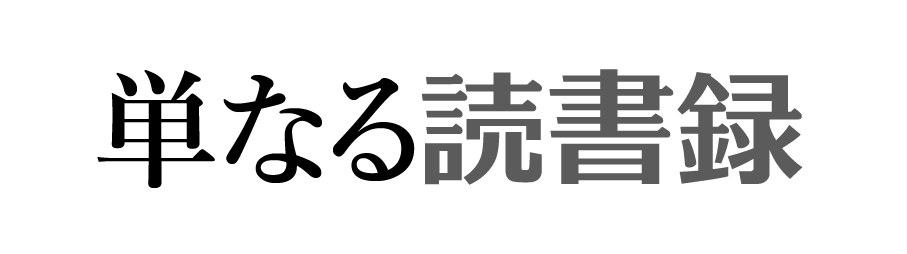農業は働かせホーダイ
労働基準法の適用除外
コメ価格の高止まりが話題だ。
農業従事者、もっといえば農業を営む事業体に身を置くものからすると、そんな結末は当たり前の話だと思う。
ニュースではコメの転売やインバウンド増加などと喧伝しているが、そもそも単純に米を作る農家が減少していること、さらには対価も安いことが根本的要因だろう。
だが、それが問題の最深部ではない。
重要なのは農業の働き方である。
農業というのは、「労働者」が働けど働けど対価の低くなる法制度によって守られていることが大きい。
つまり、農業という事業を営む上において、何者かを雇用した場合、安い賃金で働かせ放題なのである。
以前このブログにも記したが、農業は労働基準法の適用除外である。
休日も休憩も残業も(深夜労働は割増賃金が発生する)も特段、定めなくても良いのだ。
一定の賃金を払うことができるのなら、休みもなく365日働かせることも可能である。
とはいえ、有給休暇分を踏まえるとなれば休ませる必要はある。
しかし、それでも他産業に比べれば圧倒的に「キツい」労働環境と言わざるを得ないだろう。
休みなく働かせても、労基署が動く「根拠」がない
1日8時間を超え、週に40時間以上の労働をしたとしても、労基署は動かない。
なぜならそれは農業だからである。
ゆえに「就職先」として農業を選ぶ求職者は今後、ますます減少すると僕は考える。
米農家さえ後継者不足で、中山間地では農地の耕作放棄も目立つようになってきた。
農業従事者の高齢化が進むにつれ、この問題はさらに顕著になるであろう。
「雨が降ったから作業ができない、今日は休みだ」という言い分は、資本主義社会のなかにある事業者にとって、こんな陳腐化した謳い文句はない。
農作物は日に日に大きく、熟しながら生長する。
収穫時期を逃せば規格にも合わなくなる。
雨だろうが働かせることが何より重要になるのは火を見るよりも明らかである。
米農家の話にとどまらず、昨今は施設栽培に参入する農業法人も増加してきた。
全天候型のハウス内であれば、雨が降ろうが台風に吹き上げられようがなんら問題なく作業が可能である。
結果、「悪天候による休暇」はさらに遠いものとなっているのが現状だ。
そしてその環境下で労働基準法の適用除外がそのまま引き継がれている。
ものごとを裏返して考えてみると理解しやすい。
例えば、都会の真ん中に2つのビルがあるとする。
ビルAでは事務作業を、もうひとつのビルBでは近代的な農業設備を備えた農作業を営んでいる。
傍からみればどちらも外観は同じビルだ。
しかし、ビルの中で行われる作業によって働き方が随分と変わるのだ。
- ビルAでは36協定が結ばれ、残業代に割り増しが加算される。一方のビルBではそれがない
- ビルAでは朝8時から5時までの就業で、昼休憩もある。ビルBでは朝4時から夜の10時まで、休憩無しで作物の出荷作業を行っていたりする。
- ビルAでは土日祝日は休みである。ビルBでは、かれこれ入社以来、5ヶ月連勤というケースもある。こんな働き方をしたところで、給与は事務作業の従業員のほうが高かったりするのだ。
このような働かせ方をしたところで、ビルBの事業主にはなんのお咎めもない。
なぜなら「農業」なのだから。
労働基準法と照らしわせてみれば、違法ではないのだ。
ところが、事務作業の事業主が同じような労働を課したら一発アウトであろう。
とはいえ、上記の例は極端なものであり、解釈によっては適用される場合もあるだろう。
しかし、現状は「農業だから」という言葉によって、労働者が搾取される状況が今もなお継続されているのだ。
昭和の話ではない。
何度も言おう。
このような労働環境で、次世代の労働者が集まるだろうか。
別の産業に取り込まれていくのは至極当然の話であって、いつまでこのようなブラックな法を残し続けるのであろうか。
今回のコメ騒動の背景にはこうした要因も潜んでいると考えている。
農業を就職先として選ぶのには、現代日本人にとってあまりにも過酷である。