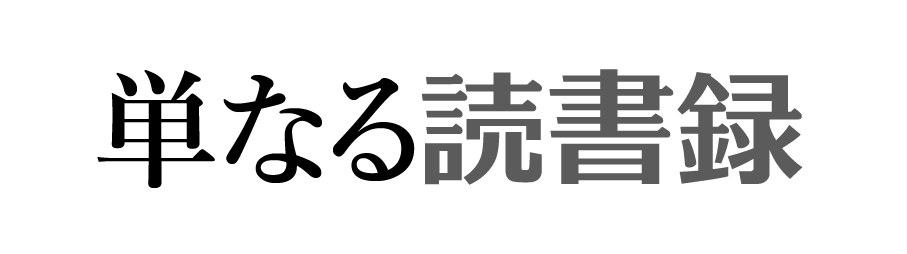本日、日本各地で「令和の百姓一揆」なるデモが行われたと、一部メディアが報じている。
コメの価格高騰が続く中、富山市で米農家や市民らが日本の食と農業を守ろうとトラクターや軽トラックでデモ行進をしました。 これは「令和の百姓一揆実行委員会」が全国に呼びかけて行われたもので、富山では 農家や消費者の市民およそ70人が参加しました。 トラクター3台と軽トラック10台に続いて、参加者たちは令和の百姓一揆という横断幕を掲げ、農家の所得補償などを訴えました。
引用元: 「令和の百姓一揆」の横断幕…コメ農家や市民等がトラクターや軽トラでデモ行進 農家の所得補償など訴える|FNNプライムオンライン
報道によると、農家の所得保証がメインではあるが、僕はそこに疑問がある。
かつてはその流通が国によって管理されていた時代があった。
食糧管理法のもと、米は国の手で買い上げられ、配給されていた。
しかし、1995年の食糧法施行により、その風景は一変する。
消費者の多様なニーズ、流通の効率化、生産者の自主性尊重といった時代の要請を受け、米の流通は自由化された。
だが、自由化に至るまでには、米を取り巻く大きな変化があった。
高度経済成長後の食生活の変化により米の消費量が減少する一方で、生産技術の向上により生産量は増加。
その結果、米価の下落が懸念され、政府は減反政策を導入した。
これは、農家に水田の転作や休耕を促し、生産量を調整することで米価の安定を図るものだった。
しかし、この政策は農家の経営意欲の低下や新たな課題を生み出し、約半世紀を経て2018年に廃止された。
これらの政策の根底にあったのが、食糧管理制度だ。
戦後の食糧難の時代、国民への安定供給と価格の安定を目指し、国が米の生産から流通、消費までを管理した。
しかし、時代が進むにつれて制度は形骸化し、自由化の流れの中でその役割を終えた。
もっとも、米の流通が完全に自由になったわけではない。
食糧の安定供給のため、政府は今も備蓄米の管理などを行っている。
そして、デモで訴えのあった補助金の投入や新規参入の障壁、高齢化による耕作放棄地の問題など、現代の日本の農業は多くの課題を抱えている。
前置きが長くなったが、そのうえで違和感を覚えるのは、農家の所得保証だけすればよいのか?という点だ。
補助金は既存の農家の経営維持には役立つかもしれないが、高い参入障壁がある現状では、新規就農を促し、生産量を大きく増やす効果は期待しにくい。
農家への所得補償・補助金投入は決して反対しないが、平均年齢が70歳近い農業者にだけ恩恵があるような制度になりえるように僕は思う。
既存農家の血縁関係にある後継者ばかりが次世代の農家となり、いまやそれすら期待できない状況のはずだろう。
やるべきことは閉鎖的な考えを脱却すること、他の業種と近しい働き方を見据え、大規模化に対応する体制をはかり、法整備を急ぐこと。
そのほかにも初期投資の大きさ、専門知識の習得、販路の確保など、乗り越えるべき壁はあまりにも多い。
さらには、高齢化した農家の死亡に伴う相続問題、特に所有者不明の農地の増加もある。
相続登記の未了や遠隔地の相続などが原因で、管理されない農地が増加し、耕作放棄地の拡大を招いている。
長い目で見て日本の農業を変えていくためには、補助金のあり方だけでなく、新規参入の障壁を徹底的に取り払い、時代に合わなくなった法律や制度を見直していく必要があるだろう。
農地の取得・利用の緩和、資金調達の支援、知識・技術習得の機会提供、販路開拓の支援、そして相続登記の促進など、多岐にわたる改革が求められる。
先述のように米の流通は自由化しつつあるが、その利権はまだ「昭和の農家」が握っている。
現在も変わらない。
次は平成・令和の農家を育成せねばならないのに、話がファウルボールのようにワケのわからない方向へ向かっているように僕には見える。
でもね。
正直なところ、米が不足している現実がある以上、もはや手遅れだと僕は思う…。