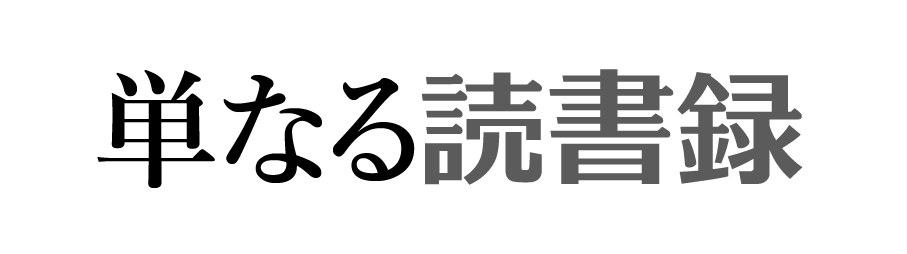東京都議会の映像を見て驚いた。
職員がスーツの襟元に複数のバッジをつけているのだ。
それも、一つや二つではない。三つ、四つと、まるで勲章のように連なっている。
バッジは通常、何かの証やアイデンティティを示すものだが、ここまで増えると、逆に何を示したいのか分からなくなる。
バッジには、それぞれ意味があるのだろう。
所属する部署のバッジ、特定の政策を推進するためのシンボルバッジ——SDGs、環境問題、LGBTQ支援など。
思いつく限りでも、つける理由はいくらでもある。
しかし、それらをすべて襟元に詰め込んだ結果、肝心の「伝えたいこと」がぼやけてしまっているように感じる。
海外ではどうなのだろうか。
アメリカの公務員は通常、小さなラペルピンをつける程度らしい。
イギリスやフランスでも、バッジ文化はそこまで目立たない。
もちろん、国ごとに文化は異なるが、日本の職員がここまで多くのバッジをつけるようになったのは、比較的最近のことではないだろうか。
バッジが増えた理由は、おそらく「やってるアピール」を重視する風潮の影響だ…と僕は思っている。
政策を推進していることを示すため、または所属を明確にするために、視覚的なサインを求める。
しかし、そもそもスーツはそうした「メッセージを発信する場」ではないはずだ。
本来、シンプルでフォーマルな服装であり、過剰な装飾は不要なもの。
それならいっそ、アメリカの大統領選でトランプがかぶっていた「MAGA」キャップのようなものを導入するのはどうか。
視認性の問題は解決するし、遠くからでも一目で「この人が何を推しているのか」がわかる。
消費税ゼロを訴えたいなら「消費税0%!」と書いたキャップをかぶる。
SDGsを推進したいなら、緑色の帽子にロゴを入れる。
これならバッジのように細かすぎて見えない問題もなくなるし、スーツのフォーマルさも維持できる。
ただ、実際にやるとすると、議会の風景が一変するだろう。
スーツ姿の職員たちが、赤や青や緑のキャップをかぶって仕事をする姿は、少し滑稽に見えるかもしれない。
結果として「公的機関がカジュアルになりすぎる」という批判も出てくるはずだ。
そう考えると、やはりシンプルなピンバッジ一つに統一するのが最適解なのかもしれない。
それにしても、バッジを増やせば増やすほど「私はこれだけのことをしています」と示したい意図が透けて見える。
しかし、本当に大切なのは、バッジの数ではなく、その政策をどれだけ実行できるかだ。
視覚的なアピールよりも、行動で示すことのほうがはるかに重要なはずだし、そもそもテレビに映し出されたバッジは小さく、何を現しているのかよくわからない。