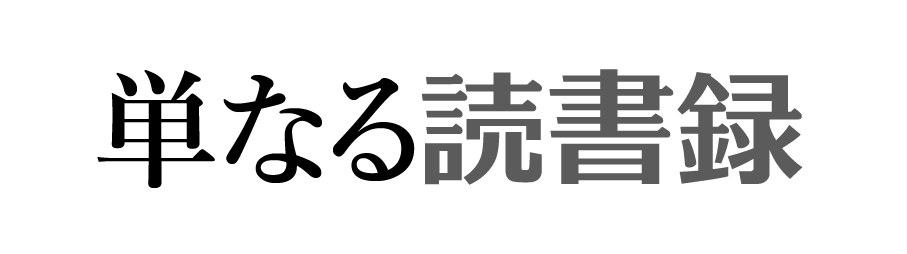デスクワークと肉体労働の疲労感
Twitterで話題に
ツイッター(X)でこんなツイートを目にした。
それに反論するかたちで、このようなツイートも。
僕も20代はデスクワーク、30代は肉体労働だったから、後者のこの感覚は超絶分かる。
デスクワークと肉体労働、その疲労の質が根本的に異なることを身をもって知っているつもりだ。
残業に用いるエネルギーは計算できる
疲労の本質的な違いは消費エネルギーだけではない。
デスクワークの疲れは頭脳の疲れであり、肉体労働の疲れは全身の細胞が発する悲鳴のようなもの。
一方は精神的な鈍さとして現れ、もう一方は文字通り体が動かなくなるという形で現れる。
昨年、甲州アルプスの70kmを走って「オレの持久力ハンパねぇ!」と思ったけど、これは8時間ほど野外の農場を動き回っていたからこそだろう。
そりゃ持久力も上がるはずだ。
そのうえ走って通勤していたから、良いトレーニングにもなっていた。
肉体労働は否応なしに身体能力を高める。
それは意識的なトレーニングとは違う、「日々、稼ぐための力」への適応なのだ。
そのうえで2時間程度の残業があると、確かに身体は悲鳴を上げる。
1日にだいたい30,000歩歩くから、2時間残業するとなると、追加で残り7,500歩。
距離に換算すると5〜6kmを何かを運びながら移動することになる。
3.5メッツで計算すれば僕の体重(55kg)で404kcalの消費となる。
立ったりしゃがんだりのインターバルも含めるから、デスクワークの2時間とはカロリー消費で考えると比較にならない。
至極当たり前な話をするが、肉体労働の疲労は質的に異なる。
それは単なる「疲れた」という感覚ではなく、筋繊維の微細な損傷や代謝産物の蓄積による痛みを伴う。
デスクワークで感じる眠気や集中力の低下とは根本的に違うのだ。
こうした疲労感というのは、実際に体験してみないとわからないものだろう。
仕事から帰れば「寝る」ということも、ある意味では「仕事」なのである。
資格試験のための時間を確保するのは現実的に難しい場合もあるだろう。
動ける人間は仕事が増えてしまう
さらにいえば、体験したからと言って「続けられる」人間は一握りである。
僕の場合は幸いにも(?)、動き続けることが求められる現場で鍛錬を積み、持久力が求められるスポーツにハマり、当然のことながら同世代の人間よりも持久力はあるほうにカテゴライズされる。
僕の場合は環境的にそうならざるを得なかったといったほうが正しいのかもしれない。
前の職場でも、そうした持続的に体を動かす仕事から逃げる人が多かった。
一緒にやっていたと思いきや、途中で持ち場を離れてスマホをいじっていたり、座っていたりする。
肉体労働の世界には見えない階級が存在する。
それは「どれだけ持続できるか」という基準で決まる階級だ。
若さだけでは克服できない耐性と意志の強さが求められる世界でもある。
つまるところ、こうした肉体労働は適応できる人間とできない人間がいるというのをまざまざと知った。
そして出来る人間はできてしまうからこそ、いつの間にかこうした仕事を回され、抱えてしまう。
現代の肉体労働は、人員不足が当然のことであるから、最後には動ける人間がひとりで作業をすることになってしまうのだ。
これは奇妙なパラドックスを生む。
能力のある者ほど仕事が集中し、さらに疲弊していく。
それでいて、その能力は当たり前のものとして評価されないことも多い。
賃金も動かない人間と同じか、若手だったら少なかったりする。
肉体労働の世界では、できることが「当然」になりやすいのだ。
持続的な作業の労働においては、動けないことを装いながら働くほうが良いのかもしれない…というのは僕にとっての学びだった。
皮肉のようにきこえるだろうが、現実の労働環境では時に真理となるだろう。
自分の能力をすべて見せれば見せるほど、より多くの負担が課せられる可能性がある。
かといって、サボってばかりいればいずれ評価も下がる。
適度なコントロールが必要となる。
デスクワークは考えすぎてしまう
一方で、デスクワークはデスクワークで、ずっと座りっぱなし…という勤務も少なくない。
むしろあらゆることを考えてしまうので、無性にストレスを覚えてしまうだろう。
僕の場合はまさにこのパターンで、なにかしら動いていないとあらゆる事を考えてしまって、不安になる。
不安になると何もできなくなってしまう。
デスクワークの静寂さが生む「思考の渦」は、ある意味では肉体労働以上に人を疲弊させることがある。
体は休めていても、脳は休まることなく回り続け、時に自分自身を消耗させていく。
肉体労働には少なくとも「体を動かした証」という達成感があるが、デスクワークでは成果が見えにくく、それがさらなるストレスを生むこともある。
ゆえに、なんだかんだいっても朝から陽を浴びて、身体を動かす仕事をするほうが性に合う。
というよりも、狩猟だろうが、農耕だろうが、人間はそのようにして生活を営んできたのであり、それをパターン化することができれば何よりの幸せだろうと感じる。
無論、考え方は人それぞれだろうが。
人類の進化の歴史からみれば、座り続ける仕事は極めて新しい現象だ。
僕ら人間の身体は動くことを前提に何十万年もの時間をかけて進化してきた。
その観点からは、デスクワークという働き方こそが「不自然」なのかもしれない。
理想は両方の良さを取り入れたハイブリッドな働き方ではないだろうか。
頭を使う時間と体を動かす時間の適切なバランス。
それが現代人にとっての本当の「健康的な労働」なのかもしれない。
身体は動かなさないと衰える
ところが。
いまの僕は仕事を辞めたので、利点だと思っていた持久力がどんどん低下してしまった。
体調不良もあって約2週間まったく動かなかったら体力、筋力、そして持久力が如実に低下したのである。
まずは走れる身体を取り戻すこと、そして維持していくことが僕の今後の課題である。
身体能力は使わなければ急速に衰える。
これも人間の身体の特性だ。
かつての肉体労働で得た能力も、維持するための意識的な努力がなければあっという間に失われていく。
結局のところ、デスクワークと肉体労働、どちらが優れているというものではない。
それぞれが異なる種類の疲労と充実感をもたらす。
大切なのは自分の性質を知り、それに合った働き方を選択できることだろう。