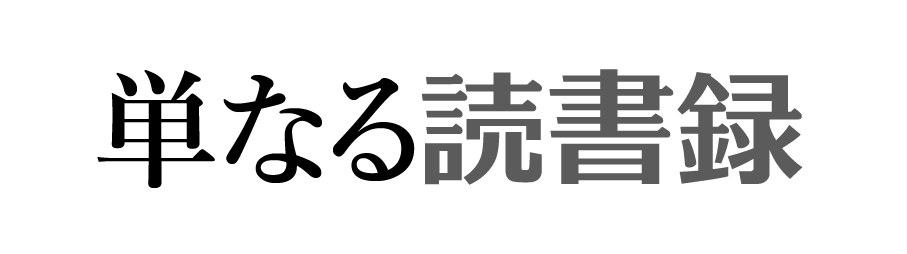前回、僕はこんなことを書いた。
デスクワークの静寂さが生む「思考の渦」は、ある意味では肉体労働以上に人を疲弊させることがある。体は休めていても、脳は休まることなく回り続け、時に自分自身を消耗させていく。肉体労働には少なくとも「体を動かした証」という達成感があるが、デスクワークでは成果が見えにくく、それがさらなるストレスを生むこともある。
ゆえに、なんだかんだいっても朝から陽を浴びて、身体を動かす仕事をするほうが性に合う。というよりも、狩猟だろうが、農耕だろうが、人間はそのようにして生活を営んできたのであり、それをパターン化することができれば何よりの幸せだろうと感じる。無論、考え方は人それぞれだろうが。
人類の進化の歴史からみれば、座り続ける仕事は極めて新しい現象だ。僕ら人間の身体は動くことを前提に何十万年もの時間をかけて進化してきた。その観点からは、デスクワークという働き方こそが「不自然」なのかもしれない。
理想は両方の良さを取り入れたハイブリッドな働き方ではないだろうか。頭を使う時間と体を動かす時間の適切なバランス。それが現代人にとっての本当の「健康的な労働」なのかもしれない。
オフィスワークと肉体労働を考える
僕自身の経験を振り返っても、朝に指示された業務とは違う仕事を夕方になって突然言われることがあり、それがこなせないことに強い負担を感じていた。予定していた業務が終わらず、頭の中では常にその片付け方を考えながら働く。最悪なのは、次から次へと新しい仕事が舞い込んでくることで、自分の優先順位と指示を出す上司の優先順位が食い違うときだ。
思えば、これは単に仕事をふってくる上役が現場を理解していなかっただけなのかもしれない。
話は逸れるが、かつて農耕を主体とした暮らしでは、「日々新しいタスクが舞い込んでくる」ということは少なかっただろう。毎年同じ作業を続け、先祖代々それを繰り返していれば、食料は確保できたはずだし、次の世代へと営みをつなぐこともできた。それが産業革命以降のわずか数百年で、大きく変わった。今ではAIの普及とともに、タスクの複雑化とスピードが加速している。
そんなことを考えているときに、映画『PERFECT DAYS』を観た。
この映画は、毎日を淡々と生きる姿を描いている。単調な生活の中にも、時折トラブルや思いがけない出来事が訪れ、「変わらない」ままではいられなくなる。それでも、変わらない日常を送ることが、ある種の幸福なのではないか、と考えさせられる作品だった。
現代の仕事は高度化し、日々違うパターンが求められる。しかし、太古の人類が狩猟や農業を始めた頃、生活のバリエーションは今ほど多くなかったはずだ。産業革命以降、人々は変化し続けなければ生きていけなくなり、同じ仕事を続けるだけでは稼げなくなった。
トイレ清掃のような業務はルーティン化されており、変化が少ない仕事のひとつかもしれない。僕自身も、変化の少ない仕事に身を置いていたので、その感覚はよくわかる。よく寝て、よく働き、よく食べる——そんな生活こそ、本来の人間にとって必要なのかもしれない。
映画を観ながら、「変わらない日常」がもしかしたら幸せのひとつなのではないかと思った。いまでは「変わらない仕事」も変化を求められ、変わらない仕事を探すことのほうが難しいだろう。そして変わらない仕事というのは、さほど賃金も高くはない。あるいは宮大工のように手に職を就けなければ、安定した仕事もなかなか得られるものでもない。
そして主人公を観ているとおもうのは、変わらないことで得られる「心地よさ」もあるけれど、それに支払う代償も小さくはない。孤独もそのひとつで、映画のラストシーンではその心模様を観ているものに刻みつける。変わらないことはむしろ、難しい。