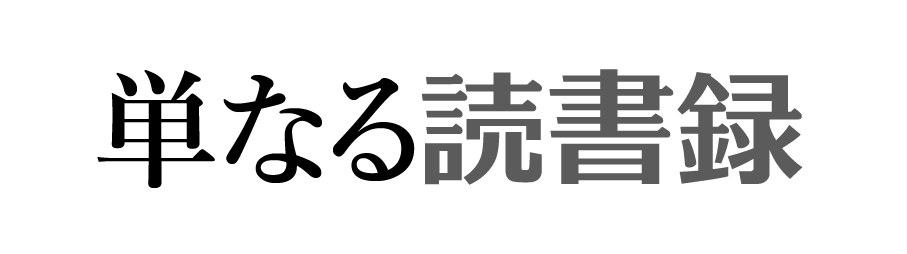肉体労働が嫌だったんでしょう?
先日、ライターの梅田香子氏が、氷河期世代に向けて放った言葉が、インターネット上で大きな波紋を呼んだ。
「就職が大変そうとわかっていたら、どうして大学生のうちに英検一級とか簿記とか、勉強して取っておかなかったのかしら?」と問いかけ、さらには建設業の人手不足に触れ、「まあ、そういう仕事は嫌なんでしょう」と続けたのだ。
就職が大変そうとわかっていたら、どうして大学生のうちに英検1級とか簿記とか、勉強して取っておかなかったのかしら?優秀な若い脳細胞なら、他の語学もいけたでしょうに。あるいは筋トレとか。建設業はいつも人手不足。まあ、そういう仕事は嫌なんでしょう。
その火に油を注ぐように、彼女は自身の境遇についても語り始めた。
若くしてベストセラー作家となり、高収入を得たのは「運がよかったからに決まっている」としつつ、夫が大工の棟梁であり、娘がフィギュアスケートのコーチであることを引き合いに出し、「ツキを大事にしている」と述べたのだった…。
一連の発言は、彼女が自身の成功を「運」の一言で片付けているように聞こえる。
それは、長年懸命に働いても報われないと感じている人々からすれば、到底納得のいくものではない。
確かに、「運」が仕事の成否に影響を与える可能性は否定できない。
僕自身、どうしようもない状況に置かれた時、「運が良い」と信じ込むことで、辛うじて前に進むことができた経験もある。
しかし、人生を、社会を、そして人々の努力や苦労を、「運」という一言で安易に切り捨てることの危険性を、今回の梅田氏の発言は改めて僕らに突きつけたように思う。
例えば、ホロコーストで命を落とした人々を「運が悪かった」と片付けることは、彼らの尊厳を踏みにじる暴言に他ならない。
努力すれば避けられたはずだ、などという言葉は、「運」という名の免罪符を盾にした、想像力の欠如が生み出した悪意と言わざるを得ない。
梅田氏と氷河期世代の人々との間には、世代間格差の経験という隔たりが横たわっている。
彼女は、その世代が味わったであろう苦難を想像することができず、安易な「努力」という言葉で、あたかも容易に乗り越えられたはずの問題であったかのように語る。
そこには、彼女自身の経験に基づかない無知ゆえの残酷さがある。
「マウント」という言葉以上の重圧と、生まれた世代というどうしようのない時間への喪失感すら伴う。
そして、彼女の語る「努力」は、結局のところ「自己責任論」という批判の的へと容易に結びついてしまう。
これらの発言で疑問符を抱くのはやはり「自己責任論」で解決できる話だったのか、どうかということ。
彼女にはその「苦役を伴う労働への前提」がない。
だから氷河期世代や、その周辺の人たちの怒りを買ってしまったのだと思う。
では、その「苦役を伴う労働への前提」とはなんだろうか。
ディスろうとしたら無知がバレちゃった
僕がこの一連の発言に覚えるもう一つの気持ち悪さは、「主語の不在」だ。
問題となったツイートを改めて見てみると、「夫は」「娘は」といった言葉が頻繁に登場する。
梅田氏が語る「努力」は、彼女自身の努力というよりも、むしろ「他人の努力」を借りて語られているように感じられるのだ。
つまり、彼女自身の幸運は、自身の努力の直接的な結果というよりも、他者の幸運(あるいは努力の結果)を、あたかも自分の手柄のように語っているのではないか。
それは、虎の威を借りるような、どこか他人頼りな印象を受ける。
もちろん、彼女自身も努力をしてきたのかもしれない。
しかし、今回の発言の主眼が「なぜ肉体労働に参加しないのか」という点にあることを踏まえれば、それはそのまま「あなた自身(梅田氏)は、なぜ肉体労働に参加しないのか」という問いへと跳ね返ってくる。
僕は、長く肉体労働に携わってきたからこそ、「嫌だから肉体労働に参加しないのでしょうね」といった安易な言葉は決して口にしない。
なぜなら、肉体労働には、確かに苦しさもあるけれど、それ以上に喜びや達成感といった、言葉では言い表せない魅力があるからだ。
簡潔に言ってしまえば、楽しいのだ。
にもかかわらず、彼女が肉体労働を「嫌なもの」と認識しているとしたら、それは彼女自身が肉体労働を苦役だと考えている可能性を示唆している。
単なる苦役であるとしか考えていないのだろう。
ディスろうとしたらかえって、ディスろうとした対象への無知が露呈してしまった結果だろう。
言うなれば、身体を動かす労働を彼女自身が経験したことがないのではないか、と僕は思うのだ。
だからこそ、僕は彼女に言いたい。
ぜひ一度日本に帰国し、僕たちが働く肉体労働の現場に来てみてほしいと。
あなたより十歳以上年上の方でも、今なお現役で活躍している人々がいるのだから。
それが難しいのであれば、ライターという職業柄、日本の氷河期世代の人々、そして彼らが置かれた厳しい状況を、実際に取材してみてほしい。
机上の空論ではなく、彼らの生の声に耳を傾けることこそが、真実を知るための第一歩となるはずでは?