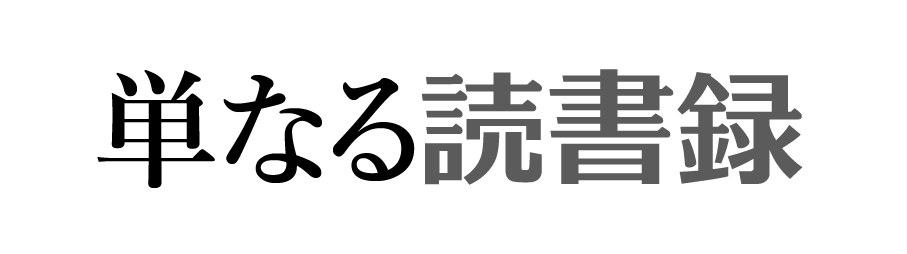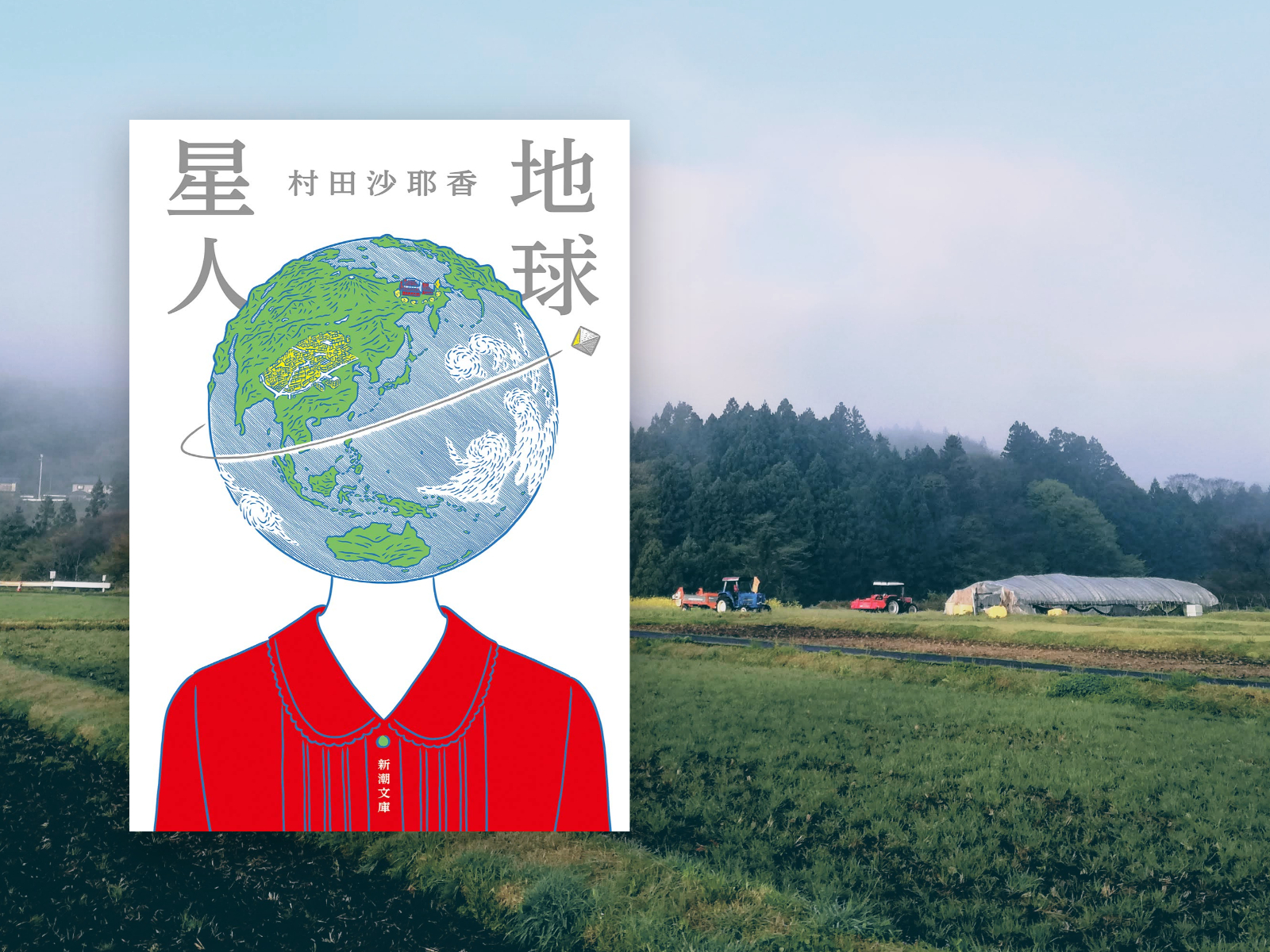「クリーンな人」と「かわいそうな人」
ドラッグストアが出来た。嫌な予感がする…
実家の見慣れない場所に、真新しいドラッグストアが姿を現した。
5月15日の開店を控え、まだひっそりとしているその小さな空間にこれから多くの人々が押し寄せるのだろう。
想像力を逞しくすれば、開店当初の慌ただしさの中で不慣れな若いスタッフが右往左往し、そこに年配の客が些細なことで声を荒げる未来が僕の目に映る。
カスタマーハラスメント、通称「カスハラ」。
「お客様は神様だ」という言葉を文字通りに解釈し、「カスハラは権利だ」とでも考えているかのような人々が存在する。
そのうえで考えてみたい。
若い世代が抱く「カスハラ」への感覚は、僕らとは少し異なるのかもしれない。
彼らは、その行為自体が社会的な制裁によって裁かれる可能性を知っている。
SNSという名の巨大な監視網の中で、瞬く間に悪事が拡散されてしまう危険性を、肌感覚で理解しているのではないだろうか。
つまり他人が「クリーン」であることを監視しているし、自らも監視もされていると認識している。
「クリーン」でない人を見るやいなや、スマホで録画しても良いという社会規範さえ持っている(可能性がある)。
「クリーン」でない人には人権はない。
肖像権もない。
なぜなら、「自らが生まれたときからクリーンであることを求められてきたのに、軽々とその基準を下回る存在が突如として現れた」から。
そして皮肉なことに、彼らはアルバイトなどを通して、「カスハラ」を受ける側に立つことが多く、「カスハラ」をする人間はそれを知らない。
以下、ネタバレを多分に含みます。
未読の方、内容を知りたくはない方はこれ以上スクロールせず、文章も読まず、そっとご退場ください。
「クリーンな人」と「かわいそうな人」
この問題を考えていると、ふと村田沙耶香氏の小説「世界99」に登場する「クリーンな人」という概念が頭をよぎる。
村田氏の作品の特徴として、「地球星人」でもそうだったように、人間を「〇〇人」と「××人」のように明確にカテゴライズし、その対比を通して物語を深く掘り下げていく手法をとる。
「世界99」には、「クリーンな人」と「かわいそうな人」という二つの明確なカテゴリーが存在する(恵まれた人もいるけれどそれは主にラロロリン人とされる)。
そして、先のドラッグストアで横柄な態度をとるであろう人々は、おそらく後者の「かわいそうな人」に該当するのだろう。
村田氏は、「かわいそうな人」を単なる「困った人」として描かない。
「汚い感情」という言葉で表現されるように、彼らは自身の意見や主張を持ちながらも、時代の変化に取り残されてしまった人々、社会から十分な理解や支援を得られなかった人々として描く。
そこには、一種の「優しい客観性」すら感じられる。
まるで、どこか人間とは異なる下等生物を観察するような、冷静な視線が文章の端々に滲み出ているのだ。
そして、物語の登場人物たちはもちろん、現実を生きる僕らもまた、心のどこかで「かわいそうな人」にはなりたくない、あるいはそう見られたくないという感情を抱いている。
「クリーンな人」でありたいと願い、振る舞う。
その結果として、社会全体が文字通り、清潔で秩序だった方向へと進んでいく…。
そんな未来が、「世界99」では描かれているのだ。
「かわいそうな人」になったのは「自己責任」?
リアルな世界でも、「かわいそうな人」に対する憐れみの視線は当然ある。
しかし、その視線には、具体的な保護や援助の手が伴わないことが多い。
むしろ、「かわいそうな人」であるというレッテルが、彼らをさらに社会から孤立させ、最悪の場合、生活の困窮や必要な支援を受け入れられない状況へと追い込んでしまう。
それはなぜなのか。
突き詰めれば、「かわいそうな人」であるのは結局本人の責任であり、「クリーンな人」になるための努力が足りなかった、つまりは「自己責任である」という冷徹な価値観が、現代社会にも浸透しつつあるような気がしてならない。
村田氏は、「自己責任において生きることに失敗した人」としての「かわいそうな人」を、タブーに踏み込みながら鮮やかに描き出しているのだ。
その感覚を言い表すような現象を、先日X(旧Twitter)で見かけた。
長くなってしまうので、別の記事に思いの丈を書き込んだ。
読んでみてほしい。
現代の日本社会は、かつて存在したであろう強固なコミュニティが崩壊し、世代間の価値観のズレから、いがみ合いが生まれ、資本主義の浸透によって金銭至上主義が蔓延している。
こうした「金銭至上主義」を根本的に解決しようとした手法も「世界99」には登場する。
後述する「記憶のワクチン」もそのうちのひとつだと思うのだが、これを考えると長くなってしまうので、後日、このブログに記録する。
「世界99」には宗教がない。
ラロロリン人のターゲットは「空っぽな人」
「世界99」のラストでは「儀式」と呼ばれる行為を通して、人類は新たな刺激を得て次の段階へと進む。
しかし、その世界では科学が絶対的なものとして信奉され、かつての宗教的な要素は形骸化しているように思える。
主人公が、儀式の形式的な荘厳さに逆に滑稽さを感じてしまう場面が、それを象徴している。
結果として、人間が生物として根源的に持っている「性」といった要素さえも、最先端の技術によって容易に改竄されていく。
社会が強く希求し、それにラロロリン人が応えた結果なのだろう。
そして、それを深く考えることもなく受け入れてしまう「空っぽな人」たちの存在が、ディストピア的な未来を加速させていく。
しかも「空っぽな人」たちはたいてい「クリーンな人」で「かわいそうな人」ではない。
「かわいそうな人」はむしろ変化に抗う存在であって、「クリーンな人」が実質的に社会を動かしている。
だからラロロリン人が国家を制御しようとするのなら、「クリーンな人」をあえてターゲットにするのは、彼らは何も考えず、コントロールしやすいからだ。
ここが村田氏の慧眼なのだ。
しかし、僕は「世界99」という物語の外側に目を向ける。
見えない異国の地では、宗教的な規範によって、そうした最新技術が拒絶される可能性もあるだろう。
そう考えると、何の抵抗もなく最新技術を受け入れてしまう日本の国民性は、ある意味で特異であり、逆に言えば、宗教的な規範を持つ国々では、同じようにはならないかもしれない。
日本には、深く根付いた宗教感覚がほとんどないのであって、そうした「空虚さ」をすら村田氏は見抜いている。
宗教の喪失は西洋でも進む
エマニュエル・トッドの著書「西洋の敗北」の中で、彼は西洋、特にヨーロッパにおける脱宗教化が極限に達し、それが精神的な脆弱性や社会的な空洞化を招いていると述べている。
宗教の喪失によって、「超越的な意味」や「犠牲の精神」が失われ、自己目的化した自由、快楽、消費が社会を支配していると分析する。
その結果、人々は何を信じて良いのか分からなくなり、共同体も崩壊したことで、個人は「快楽」「消費」「自我の欲望」を満たすことだけを目標とするようになる。
言い換えれば、共同体の利益よりも個人の利益を追求することが第一となり、精神的、文化的なニヒリズムが蔓延してしまう。
それが西洋の弱さ、ひいては敗北につながるだろうと、トッドは警鐘を鳴らす。
一億総ピョコルン化計画
村田氏の描く「クリーンな人」の行き着く先は、もしかしたら国家の衰退なのかもしれない。
ラロロリン人が必死に新たな国家像を追い求めようとする一方で、社会を担うはずの人間たちが、どんどん可愛いだけの「ピョコルン」へと変貌していく。
一億層ピョコルン化を目指そうとしているのだろう。
しかし、国民の大半がピョコルンになると国民が不在となる。
ピョコルンにはおそらく人権がないのであって、人間として存するあらゆる権利が、ピョコルンになった際に放棄される。
別のみかたをすれば安楽死が合法化されたようなものでもある。
だが、多くの人が自ら進んで死んでしまうと国家として立ちゆかなくなり、不都合なので、結果的に編み出されたのが物語に登場する「記憶のワクチン」の存在なのだろう。
「記憶のワクチン」をどう考えるか
これは特級呪物だと僕は思う。
「記憶のワクチン」によって新たな倫理観や道徳、規範意識を国民全体に植え付ける可能性を秘めている。
法律を変え、そうした「法の記憶」をワクチンにインプットしておけば、いちいち知らしめる必要もなく、遵守させる努力も殆どいらない。
ゆえに、宗教が形骸化してしまった社会において、強引な形ではあれ、社会的な統合が可能になるかもしれない。
しかし、そこには個人の精神的、文化的な自由はきっと存在せず、「調合」によって徐々に人々の記憶が、思想が、精神状態がコントロールされていってしまう。
「記憶のワクチン」の接種の可否は個人によって委ねられているが、ある種において覚醒剤やドラッグのように人間を頽廃させるものでもあるように思えるし、逆に言えば国威発揚にもつかえる。
それを肯定的にも否定的にも表現しているところにこの作品の重要テーマが隠されているように思う…。
「世界99」の書かれていない続きを想像することは、読者にとって一つの楽しみであり、同時に村田沙耶香氏からの問いかけ、あるいは試験なのかもしれない。