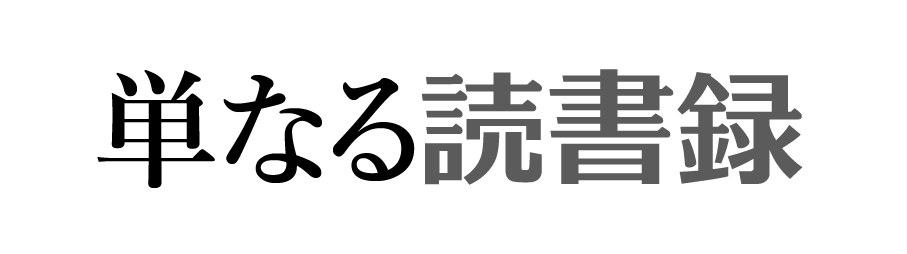「呼応」と「トレース」は高度な能力
「世界99」という小説には、実に様々なテーマが散りばめられている。
それらひとつひとつを拾い上げ、深く掘り下げていこうとすると底なし沼のように、どこまでも続いていくような気がしてしまう。
それほどまでに、村田沙耶香氏のこの作品には、あらゆる思想と社会に存在する様々な齟齬が詰め込まれ、読者にある種の重圧感を与える。
それは、良い意味においても、悪い意味においても…だ(笑)。
今回、僕が特に深く考えてみたいのは、この小説の一大テーマとなっている「呼応」と「トレース」について。
以下、ネタバレを多分に含みます。
未読の方、内容を知りたくはない方はこれ以上スクロールせず、文章も読まず、そっとご退場ください。
「呼応」と「トレース」のテーマの下敷き
このテーマは、既刊の「生命式」に収録されている「孵化」という短編小説の中にも、その萌芽を見ることができる。
というより、著者の村田氏自身も語っているように、「世界99」はこの「孵化」という小説を下敷きにして生まれた作品。
だから僕は、「世界99」を読む前の、いわば予習として、この「孵化」を読み直してみた。
以前に書いたその時の感想は、以下の記事に。
「世界99」を改めて読み返して思うのは、「呼応」と「トレース」という行為は、人間にとって高度な能力であるということ。
いわゆる「EQ」が高いと言い換えることができるだろう。
むしろ現代の社会においては、こうした能力が様々な場面で求められているのではないか。
そもそも古くから、僕らの社会・コミュニティにおいてはカメレオンのように、その場その場で人格を巧みに変えられる人が、生き抜く上で必要とされてきたのかもしれない。
会社という場であれば社会人としての顔、子供を持つ親たちの集まり(いわゆるママ友など)との間では親としての顔、そして旧友との同窓会では、あの日のように学生時代の顔を演じ分ける。
僕らは、意識するかしないかにかかわらず、それぞれの場所や空間において、暗黙のうちにその場に適応した「顔」(小説の中で言えば、それぞれの「世界」)を求められているのだ。
それはまさにTPOという言葉で表される具合に、服装のように、状況に応じて変化させるべきものなのかもしれない。
むしろ、置かれた場所によって自分自身を変化させることができる人間こそが、「大人」と認定される。
まだ社会の荒波を知らない小学生には、そうした器用な振る舞いは難しい。
どんな場所でも、自分の家にいる時と同じように過ごしているとしたら、社会的な信用を得ることは難しいだろう。
人間が成熟していく過程で、村田氏の言う「呼応」と「トレース」という能力を習得し、社会性を少しずつ育んでいくのだ。
過疎地では「呼応」と「トレース」はあまり要さない
ただ、正直に告白すると、僕はこうした状況への対応があまり得意ではない。
元来、内向的な性格であるということに加えて、時折、幼稚で稚拙な受け答えをしてしまうことが多い。
特に、過疎地に長く身を置いていたおかげで、地域特有の濃密な人間関係に慣れてしまい、社会一般には受け入れられにくい言葉遣いや距離感で人と接してしまうことがある。
そうした濃密な人間関係が築かれている場所では、いつでも誰とでも同じように、飾らない自分で接することで、ようやくそのムラの仲間入りを果たすことができる。
なぜか。
常にどこかよそよそしい態度でいると、そのコミュニティの中では異質な存在として扱われてしまうからだ。
ゆえに、一度「トレース」してしまうと、それをずっと引きずってしまい、同じような「呼応」を繰り返してしまうことになる。
言い換えれば、それは、その程度の深さの人間関係しか築けていなかった証左だろう。
そして、過疎地の現実は、そうした人と人との繋がりが人口減少とともに少しずつ消滅していくことも見え隠れする…。
それが、神奈川県の実家に戻ってくると、その場その場で「顔」を変えることを求められていると感じることが少なくない。
こうした都市部では、人間関係が複雑に絡み合い、初対面の人や自分とは異なる立場の人間と接する際には、瞬時に「顔」を変化させなければならない。
最初の印象、最初のコミュニケーションで躓いてしまえば、異物のように爪弾きにされてしまう可能性が高い。
ゆえに、服装や身だしなみなど、社会が徐々にルッキズムを重視するようになる背景には、それが「富」を稼ぎ出すための、一つの手段であるという側面もあるのだろう。
とくに、出会って数秒で決まる「第一印象」が、以前にも増して重要視される傾向にあると思う。
その瞬間に、その人の人間性そのものが判断されてしまうのだ。
僕の場合、上記の観点からも対人関係における経験不足を感じさせたり、状況への対応力という点で、何らかの難があると瞬時に判断されるのだろう。
そして、過疎地での濃密な人間関係とは異なり、都市部での希薄な人間関係においては、深く付き合わなくても、代替となる人間関係がいくらでも存在する…。
要は、そこにいてもいなくても変わらない(と思わせてしまう)のが、都市部での生活のメリットでもあり、同時に、深く孤独を感じさせるデメリットでもあるのだ。
話が少し逸れてしまった。
関係する人間の数が多くなればなるほど、この「呼応」と「トレース」という、高度な職人技のような技術は、現代を生きる僕らにとって、必要不可欠な能力となっているのは間違いない。
「呼応」と「トレース」は疲れる
故意か、無自覚か。
冒頭で小学生の話をしたが、僕らはいつの間にか、「呼応」と「トレース」という術を自然に身につけている。
そして、いつの間にか、無自覚的に「呼応」と「トレース」を繰り返し、他者と円滑に接触できるようになる。
それは先に述べたように、社会におけるマナーであり、ルールであるからであって、そうした行為を半ば強制されるような場面も、当然のように生じてくる。
ここで僕が深く考えるのは、その「呼応」は、本当に「無自覚的な呼応」なのか、はたまた、無意識の仮面を被った「演技による呼応」なのか、という問題だ。
以前、僕がとある会社で仕事をしていた時のこと。
それまではごく普通に、世間話などをするような間柄だった後輩がいた。
ところが、彼が会社を退職した途端、まるで別人のように口調が変わり、やけによそよそしい敬語を使うようになったのには驚いた。
その時、僕は彼に「いつもの君でいいよ、その話し方、なんだか気持ち悪いからやめてよ」と冗談めかして言ってみたものの、彼の対応が変わることはなかった。
彼は恐らく、その時の僕と彼の関係性を冷静に鑑みて、言葉遣いという名の「顔」を変化させたのだろう。
これはきっと、彼なりの社会におけるルールやマナーに沿った、ある意味で正当な対応だったのだと思う。
さらに言えば、それは社会的に求められる行為であり、社会性という観点からすれば、むしろ批判されるべきものではないのかもしれない。
が、いかんせん、僕の個人的な感情としては、どうも割り切れない気持ち悪さを感じてしまうのだ。
「自覚的な呼応」が、もし相手にバレてしまった場合、それは相当気まずい状況になるだろうし、演技をしている本人が、その演技を見透かされているのだとしたら、それもそれで、なんとも居心地が悪い。
「呼応」と「トレース」の前に…
言うなれば、この「呼応」というのは、それだけ自分と相手との関係性を瞬時に「トレース」し、一気に「呼応」という名の対応を繰り出していくという点で、甚だ高度な技術なのだ。
そして、小説の上巻などでも、主人公がある特定のコミュニティの中で見事な「呼応」を見せている輪の中に、突然、全く別の「世界」の住人が闖入してくるシーンがある。
この時、その場の状況を瞬時に判断し、それぞれの他者と自分との関係性を考慮した上で、適切な「呼応」を即座に発動させなねばならない。
「呼応」と「トレース」の前に、場面の状況を瞬時に、的確に認識する「状況把握」という能力も必要となる。
それは、想像をするだに精神的な疲労感を伴うだろうと、僕は思う。
「呼応」と「トレース」だけでも、神経をすり減らすような疲れる行為なのにも関わらず…だ。
人間を観察するというこの行為も、主人公は甚だ能力が高いのだ。
先述したように、こうした「呼応」や「トレース」の必要性が少ない地方では、その場その場で自分を合わせる必要がないため、比較的そうしたことへの疲労感は少ない。
「オレはこういう人間だから」という、ある意味で開き直りのような態度で、社会の中で存在することができる。
ゆえに、こうした高度な技術を持ち合わせている主人公は、基本的に、どんなコミュニティにおいても、その存在を許されているように見える。
むしろ、生まれ持ってして習得した技術であるかのようにも思える。
上巻を読み進めていくと、家族との接し方からして、「呼応」と「トレース」を呼吸をするかのように用い、場面に応じて人格を増やしながら接することが、ごく当然の日常であったようにも読み取れる。
そして、その高度な「呼応」「トレース」という技術によって、主人公は、常に「クリーンな人」としての地位を保ち続けることができているのだ。
ただし、その内面はどこか空虚で、まるで生きた心地もしていない。
おそらくは、そうした巧みな処世術の裏側で、「自分」という確固たる核のようなものを見いだせなかったからだろう。
そうした、言葉にはされない暗喩のようなものが、この主人公の深層心理の中に隠されているように、僕には思えてならない。
「呼応」と「トレース」を過度に行うことは、かえって自分が何者なのかを見失ってしまう……という、作者からの静かな警句なのかもしれない。
若者は「呼応」と「トレース」を求めて
だからといって、僕は、安易に呼応とトレースの少ない地方の方が住みやすいとは思わないけれど。
なぜなら、「社会的な呼応とトレース」を学ぶ機会は、往々にして過疎地では限られており、自らの立ち位置や存在意義が曖昧な若者は、総じて、より多くの可能性を求めて都会へと出ていくことを目指すからだ。
ゆえに、「呼応」と「トレース」は、多かれ少なかれ程度の問題であって、それは現代社会を生きる僕ら誰にでも、持ち合わせるべきスキルなのだろう。
この小説を読み進めながら、僕が強く感じたのは、こうした複数のペルソナを洋服を着替えるように使い分けている人は、決して少なくないのではないか…ということだった。
そのような社会の荒波を器用に乗りこなしている人たちは、比較的、社会的に高い地位にいることが多いのではないかとも感じる。
だって、それが、僕らが、僕らの周囲にある「世間」が、いつの間にか身につけてしまった「大人」という鎧なのだから。