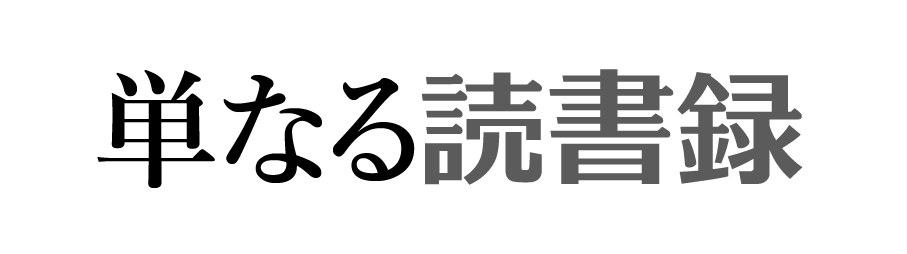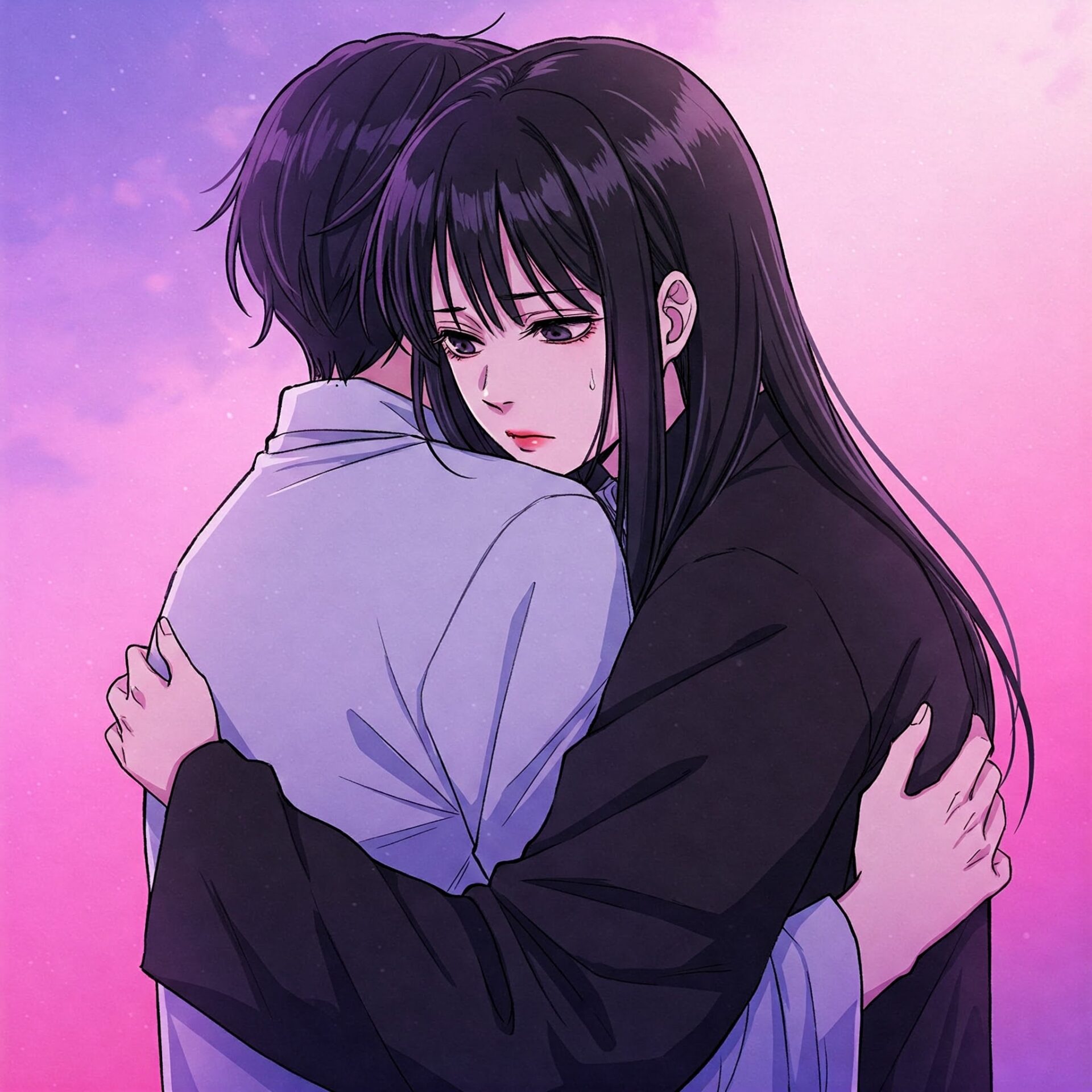「世界99」にはなにかが足りない?
男が読むとダメージを受ける可能性アリ
村田沙耶香氏の小説『世界99』を読んだ。
まず、上巻はその世界の理解を深めるもので、そして下巻は応用編という印象を受けた。
どんな勉強でもそうだが、理解しようと自ら積極的に学習しているときが一番楽しい。
しかしながら、ある程度の基礎的な理論を知ってしまうと、途端に面白くなくなることもある。それゆえ、僕は下巻が退屈に感じられた。
それは、僕が男だからそう思ってしまったのかもしれない…。
以下、ネタバレを多分に含みます。
未読の方、内容を知りたくはない方はこれ以上スクロールせず、文章も読まず、そっとご退場ください。
この作品は、男に対して、いや「男社会」に対して、村田沙耶香氏が強烈なパンチを繰り出している。
上巻はその傾向がとくに強い。
ガードなしにこれらのパンチを食らえば、一般的な男性はたちまちノックダウンするだろう。
僕もその一人だ。
村田氏は世界99の出版にあたって、インタビューの際にこう述べている。
私は、自分を麻痺させることで生き延びてきた気がします。幼少期、自分を故障させずには生きてこられなかった。今回も一章を書きながら記憶が蘇り、なんならもっとひどかったなと思いながら書いていました。
高校生の時ですら、痴漢にあっても「絶対勘違いだよ」「自慢?」みたいなことを言われたことがありました。幼少期はそういうことがもっとありました。空子たちと同じように、私も以前は「被害者」という言葉を使うには、誰がどう見ても明らかに「被害」という感じでないと、「自意識過剰だよ」と言われて逆に傷つけられるという恐怖がありました。
引用元: 『世界99』(上・下)刊行記念インタビュー 村田沙耶香「小説の中にある刃物を自分に向けていたい」 | 集英社 文芸ステーション
僕はこの本を読んで、世の女性が皆、この作品の登場人物のように考えているのなら恐ろしいとさえ思うし、罪悪感を覚えた。
それは村田氏の実体験に基づくフィクションであり、だからこそ生々しく、すぐそこにあるような出来事にように感じさせられる。
そうした部分が無自覚に、加害性を持っている可能性があるな、と思わせるのだ。
「どうしたん?話聞こか」はもはや罪
「どうしたん?話聞こか」というネットミームがある。
性欲を隠しても隠しきれないでいる男性をよく現していて、それを具現化した印象的なイラストも出回っているのだが、こうした「どうしたん?話聞こか」程度の接触ですら女性に抱いてはいけない世界を表現しているようにも思える。
いわば「性欲を隠し持って、あるいは下心を持って女性に接近する」こと自体がこの物語では禁忌であるように描かれている。
そう感じる理由の一つは、女性は基本的に「性欲がない」という前提でこの物語は紡がれているように思えるからだ。
いや、主人公にも性欲があることを自認するのだが、そのときは匠くんや明人のような男性側の性格に憑依して性欲を処理するようになる。
つまり、女性としての性欲の発露が見られない。
性欲という機能を使用(というか作中では「消費」に近い)するには暴力性を持った男に変身する点。
二つ目の理由は、ピョコルンが人間の性を処理することによって、生命が遺伝子を残すという根源的な生物的行為を人間の(ラロロリン人の)集合知が否定してしまっていること。
そのことが「世間体」からすると「クリーン」であると表現される。
作中では、人間同士のセックスがタブーであって、ピョコルンという動物によって性は「処理」される。
いわば「性」をハレとケのケに深くしまい込んで、人間という生身の存在から遠い場所へと追いやってしまった。
そして三つ目の理由は、人間に性欲を覚える男性がことごとく悪者扱いされ、最後にはある意味、殺されるという末路をたどること。
男性が人間を性的対象と見ることにおいても「犯された」と表現されるのは、男性にとっては手痛い。
これら三点において考えさせられるのは、「性欲」とは何か…ということ。
特に性欲はよく「本能」であると語られるが、この物語の中では本能を抑えることがすなわち「クリーンな人」としてみなされ、社会的に良識ある人間として生きていける。
世界99には性欲を持つこと自体は否定されないが、性欲があることはふしだらであるという様態が極めて過度に進行したものと受け止められる。
この点についてもインタビューで
でもそういう空子も、ラロロリン人が被害にあった時に被害者をジャッジする目で見るんですよね。その場面は、なぜかどうしても書きたくて。あの頃の、「私はきっと被害者検定に合格できない」と思って声を出さなかったことが、自分から自分への加害としてすごく残っています。なので主人公の加害は小説の中に存在させたいと思っていました。主人公は一貫して空っぽでありつつ、加害者でもあり被害者でもあるんです。
引用元: 『世界99』(上・下)刊行記念インタビュー 村田沙耶香「小説の中にある刃物を自分に向けていたい」 | 集英社 文芸ステーション
と語っている。
つまり、村田氏が考える性欲とは「無自覚に加害性を持ってしまう欲求である」とも読めると同時に、性欲がないがゆえに「無自覚に攻撃されてしまう」存在があることも小説では触れられる。
その結果として、その性欲が他者に向けられた途端にすべからく「暴力」に変わってしまう。
そのような世界であるのならたしかに、性欲の発露自体はすべてタブーになるのは致し方ない…と僕は思ってしまう。
「イエ」から「カイシャ」へ
僕はこの小説を読んで「女性(という性別の役割)が二つに分かれた」感じを受けた。
一つはイエというものに奉仕する女性と、もう一つは現在の男性程度の役割を設けて社会進出を加速させた女性のいる世界だ。
イエに固執しなくなった、作中で言えば苦役のなくなった女性は何をするのかと言えば、おそらく「労働」であって、社会的に労働のみを行う男性の立場と極めて近いところに女性を置くことになる。
ピョコルンは苦役する人間とのあいだに存在するバッファーのようなものであり、家事や妊娠・出産といった、女性が担ってきた苦役を引き受ける存在としても利用される。
しかし、ピョコルンを家に引き入れるのには高額な費用がかかり、そう考えると収入の低い女性は今と変わらず家事や出産を担わなければならない。
本作でその役目を演じているのがアミちゃんだろう。
また、主人公も白藤さんもピョコルンで完了しなかった家事労働を引き受けている。
女性から進んで「暴力」から逃避し、その「暴力性」にピョコルンをあてがうことで、「性」という概念がなくなった。
そのおかげでこの世界の中ではきっと、女性の社会進出が進む。
欲を言えば、だからこそ、ラロロリン人などの「恵まれた人」以外の、その後の世界②のアケミさんなどの人生や生活が、どのように変わったのかも描いてほしかった。
男の僕が読んだら「性愛」のないことが気になる
また、作中には「性愛」があまり描かれていない。
人間には「好きになっちゃう」といった本能的な感情を抱くことがあるのだが、作中では音ちゃんと白藤さんの感情の中にのみあって、それが確かなものとしても描かれてはいない。
恋愛感情をめぐる描写はほとんどないのだ。
主人公からの視点で見れば「性愛」は受け取るものであって、芽生えるものでもない。
ただし、それが音ちゃんにだけは芽生えたのだが、そこに「性的なもの」の存在は示唆されず、恐らく人として惹かれるものがあるという程度。
主人公はアセクシャルなのか、単にクールなだけなのか…。
これはもしかすると、主人公がそれまで「性愛」といったものを知らなかったがゆえに、内的感情として表せなかった…という作者の表現なのかもしれないが。
それでも読後に思うのは「愛がないなぁ」ということだった。
恐らくこう感じるのは僕が男性で、消しゴムを拾ってもらった女子を好きになっちゃう程度の恋愛経験しかないからだろう。
僕はこの手の器が狭いからその程度の感情でしか、性愛なるものを拾い上げられなかったし、だからこそ下巻が退屈に思えた。
「性愛」のようなものが、「世界99」のなかでどのように揉まれ、どのように変化するのかを僕は心のどこかで期待していたし、それが下巻における物語性の根幹のような気がしていた。
しかし、人間がピョコルンを好きになっちゃう、あるいは「未だ人間に恋愛感情を抱く」他者の存在(しかもそれはアウトロー)がチラッと現れるだけで、そこに説得力や現実味がない。
「社会的に、みんながピョコルン好きだっていうようになったら、オレもピョコルン好きになっちゃうのかなぁ?オレならたぶん、あいも変わらず人間も好きになっちゃうだろうなぁ、会話もできるし、意思疎通もできちゃうし」などと、読みながらに感じてしまう。
そうした要因から、上巻からのワクワクが下巻を読み進めるうちに冷めていったというのは、事実であり、足りない部分ではあったように思う。
下巻では人間に「性欲」を抱く男の存在が稀有のように描かれ、尚更困惑する。
とはいえ、読む人が変われば、もう少し違った解釈を受ける部分でもあるだろう。
こうしたことを踏まえると、村田沙耶香氏のパンチは鋭く、僕は少し女性不信に陥る。
女性の本心(なるものはもともとわからないのだが)が分からなくなる。
村田氏は「世間」に切り込んでいく
「かわいそうな人」を公平に、強制的に排除する
主人公の住む世界は80%の「クリーンな人」と10%の「恵まれた人」が優先的に生存権を与えられていて、それ以外の「かわいそうな人」は過度に、社会的に放置されている(ように見える)。
それにもかかわらず、人間の持つ根源的な感情や記憶はそうした「かわいそうな人」が持っているのであって、社会からの理解が得られず、だからこそ幸せではなくなってしまう。
もちろん「(人間に向けられる)性欲」などを持っている人間は「かわいそうな人」であり、だからこそ公平性を期してフラットにしなくてはならない…。
そして「かわいそうな人」には、上記の暴力性を未だ持っているのであって、その改善策としてある種、強引な方策が取られようとする。
それが「記憶のワクチン」なのだろう。
村田沙耶香氏が描く世界99は、空っぽな人たちが、「ウエガイコク」や「ラロロリン人」などの操作によってどんどん変容させられていってしまうディストピアであって、では、その変容させられる一般人とは誰なのかと問われれば、「世間」だと僕は思う。
怒り、悲しみなどの感情を持つものは生きるのに苦しい。
そうであるのなら、そうした苦しみがなくなれば幸せに生きていけるのだろう…という皮肉めいたラストになっている。
その象徴的な存在が白藤さんであり、彼女は空虚な世間に常に反抗する。
しかし、「空っぽな世間」は自らの「空っぽな欲望」によって、虚無化していくのだ。
村田氏なりの未来の想定
村田沙耶香氏はいつもタブーに切り込んでいく。
「世間はこうだから、こうだよね」といういつの間にか知らない間に形成された「無自覚」を村田沙耶香を読むと「そう言われてみればおかしいよね」と気付かさせてくれる。
しかし今作は、もっと奥深い場所へ踏み込んで「人間」「性」「生物」など、本来は変えようのない、先天的なものが変容した場合を想定している。
科学技術が進むにつれ、実際にそうなる可能性もあるだろう。
人間という生物に生来備わっている機能を、社会性によって除去・変更する動きが来たとしてもそれはおかしくはない。
そうなったときにこうなるんじゃない?という提起をこの作中で僕は感じた。
仮に現実の世界でそうした変化が起こるのなら、世界的規模で訪れるのだろうが、それを阻むのは「宗教」なのかもしれない。
そんな話を次回は書いていこうと思う。