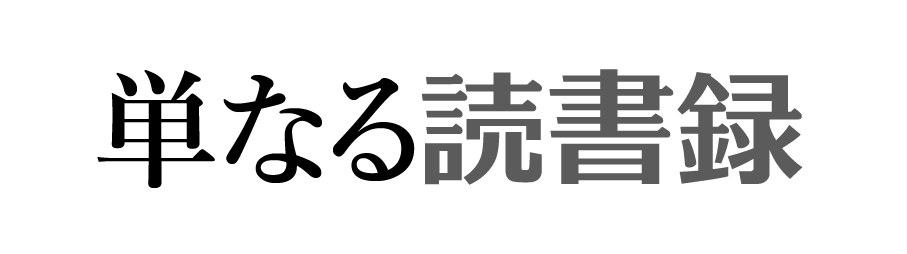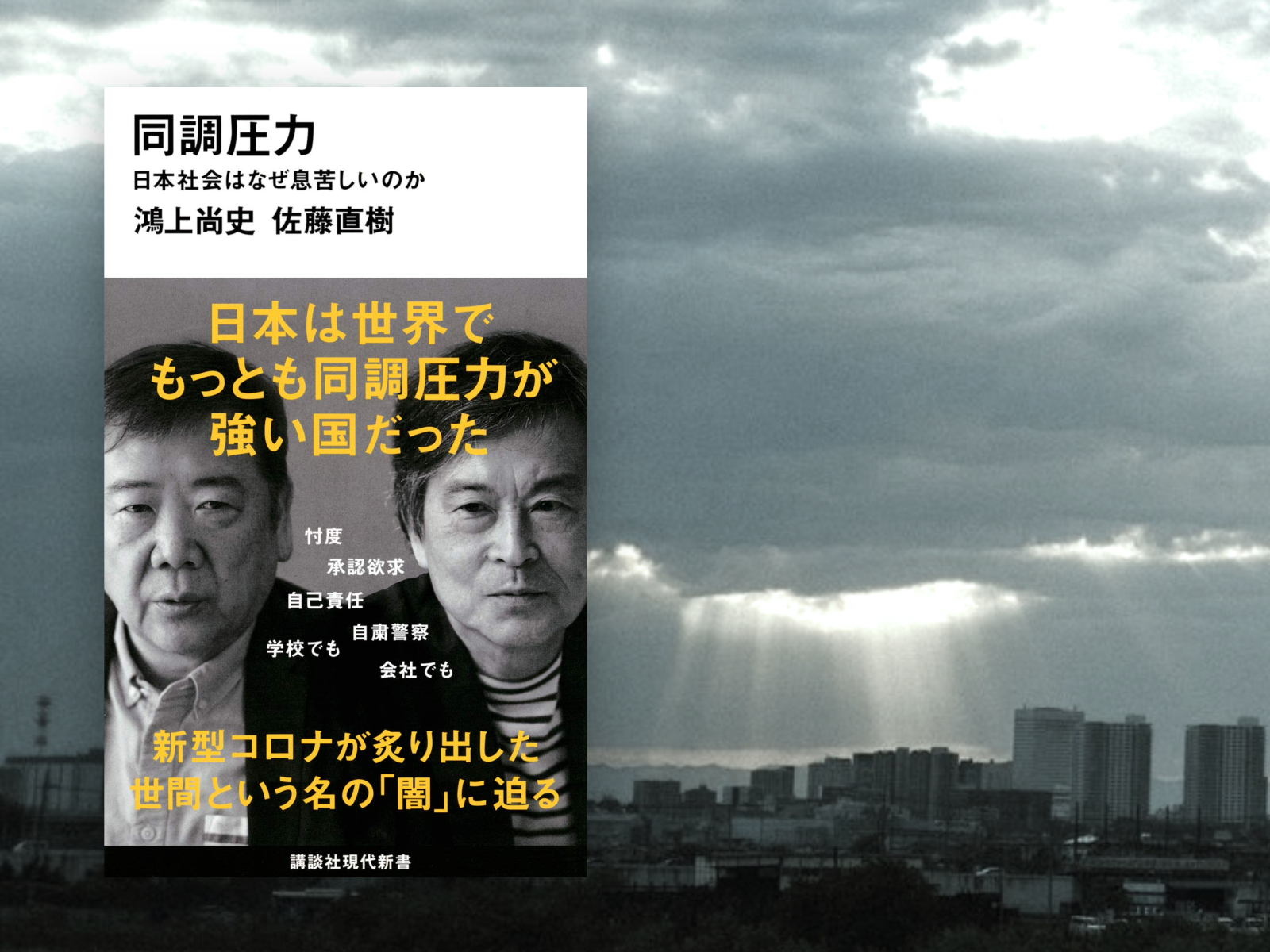ウクライナ危機に直面して感じたこと
「ロシアは悪で、ウクライナは善」って…?
2022年も幕を開けた頃。
ロシアとウクライナの情勢に世界は一喜一憂していました。
侵攻はあるのか、ないのか。
一時的に、侵攻する可能性がロシア側から否定される報道もありましたが、残念ながら2月24日、ウクライナは戦火に見舞われてしまいます。
この侵攻を受けて西側諸国は一致してロシアに経済制裁を行うことを表明。
日本もその意志をアジア諸国の中でもかなり早い段階から表明したといわれています。
そんな報道を受け、あらゆる場所に設置された募金箱は「ウクライナ人道支援」と銘打たれ、テレビでは連日、ウクライナ関連のニュースを繰り返し流します。
それをみた多くの国民が「ロシアは悪で、ウクライナは善だ」のような、ある種の思考停止に陥いっているかのように僕には思えたのです。
もちろん、一方的に侵攻し、ウクライナに住む住民を殺害したり、住居を破壊するロシアの行為は許しがたい暴挙であるのは否定しません。
ただ、その報道を正面から受け取るのではなく、あらゆる角度から認識することも大切ではないのだろうか、と思うのです。
たとえばこのまま強烈な経済制裁がロシアに及べば、当然ながらロシアにも「ロシア国民」がいるわけで、昨日までの暮らしが一気に覆される可能性だってある。
どこの国のどの国民にも「イデオロギー」があり「愛国心」があるわけで、経済制裁を続けるだけでロシアを「成敗」できるわけではなく、ロシア国民の間で他国への憎しみが醸成され、かえって情勢は悪化するだろうと僕は考えています。
それが現在、プーチン大統領への支持率上昇という結果として現れているのであり、その動きを捉えない状態のまま、経済制裁を天誅かのように支持してしまうは如何なものなのでしょう。
大切なのはどこまでいっても「対話」であり、「交渉」であるわけで、次は始まってしまった戦争をどう終わらせるのかが重要なフェーズになるはずです。
というより、戦争が長引けば長引くほど尾を引くわけで、その影響は遠く極東の島国に住む僕らにも及ぶ。
換言すれば、慎重な対応を行わないことで、とてつもないしっぺ返しを食らう。
だからこそ、わが国の立場と存立を考えることと同時に、戦中である双方の被害を少なくするためにも、早急に停戦が行われるように働きかけることが重要だと、僕は考えています。
「ウクライナ人道支援募金」は数あれど…
そうした僕の不安を口に出せば恐らく、現在では猛批判が起こるはず。
すでに職場で「経済制裁で困窮したロシア国民に僕は募金したい」と口にしたところ、「ロシア国民は家族が殺されないから幸せだ」とか、「ロシアには資源や食料があるから大丈夫だ」とか、型にハマった反論が返ってきました。
そもそもウクライナへの募金箱には「人道支援」と書かれているのであり、「人道」であるならばその対象は国家ではなく、そこに住み困窮する市民への寄付になる…と僕は考えます。
ならば極限まで市民が困窮した場合「ロシア国民への募金」もあってもそこまで批判されるものではないはず。
戦争が始まってからは、どのマスメディアをはじめ、あらゆる媒体では、ひとつのベクトルに向いた意見のみしか許されない。
ほんとうはあらゆる選択肢や、いわば「妄想」が考えられるのに、それらを潰して誰かの意向に「忖度」をしようとする。
それを日本国民全体で行おうとするのだから、気色が悪い。
いや、戦時中のロシアでは、情報統制が行われ、現に自由な発言が許されないのだから、緊迫した情勢の中では発言をコントロールすることが安易で手っ取り早いのでしょう。
けれど日本は戦時中でもないのに、常に情報統制。
「ロシアに募金を!」なんて言った途端、どうしてこうして叩かれます。
それってどこか変。
「同調圧力」という本を読む
そんな昨今、僕が読んだのはその名もずばり「同調圧力」という本。
評論家の佐藤直樹さんと、演出家・作家の鴻上尚史さんの対談本です。
本をざっくり要約すれば、
日本国民には「世間」という「同調圧力」があり、それらを暗黙の裡に遵守することで自らの存在を、世間のうちに肯定しようとする。
結果的に世間という枠から逸脱しようとする「社会」という集団は日本に根付かず、世間のルールが強化され、年々生きづらくなる
というもの。
まさしくその通り!と、本の内容の大部分を僕は共感を持って読んでいました。
世間とはなにか
まず、鴻上さんは「世間」と「社会」について
鴻上 おそらく学者である佐藤さんと、作家である僕では、語るべき言葉の質が違う と思います。まずは僕からその違いについて説明させてください。僕がいつも単純に 説明しているのは、「世間」というのは現在及び将来、自分に関係がある人たちだけで 形成される世界のこと。 分かりやすく言えば、会社とか学校、隣近所といった、身近 な人びとによってつくられた世界のことです。 そして「社会」というのは、現在また は将来においてまったく自分と関係のない人たち、例えば同じ電車に乗り合わせた人 とか、すれ違っただけの人とか、映画館で隣に座った人など、知らない人たちで形成 された世界。つまり「あなたと関係のある人たち」で成り立っているのが「世間」、 「あなたと何も関係がない人たちがいる世界」が「社会」です。ただ、「何も関係がな い人」と、何回かすれ違う機会があり、会話するようになっても、それはまだ「社会」 との関係にすぎませんが、やがてお互いが名乗り、どこに住んでいるということを語 り合う関係に発展すれば、「世間」ができてくる。
引用元:同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか (講談社現代新書) p.31
と述べている一方、佐藤さんは「世間を構成するルール」には、
- お返しのルール
- お中元・お歳暮のように貰ったらお返しをしなければいけないなどのルール
- 身分制のルール
- 年上・年下、目上・目下、格上・格下のような身分が関係の力学を決めてしまうルール
- 人間平等主義のルール
- 中根千枝さんの言葉から引用したという、同じ時間を過ごすから仲間であり、能力や才能を認めずに平等であるとするルール
- 呪術性のルール
- 香典返しのように、俗信・迷信に基づくルール
の4つのルールが存在すると述べています。
そのうえで日本には「個人(individual)」が居ないと説きます。
もう一つの意味がまさに、「個人がいない」ということなんですね。 「世間」にはイン ディビジュアル (individual) が存在しません。 「個人」という言葉も、じつはインディビ ジュアルという言葉を一八八四年ごろにヨーロッパから輸入して訳した造語なんです ね。じゃあ今、インディビジュアルが存在するかというと、英語のインディビジュアルと、我々が普通に使っている「個人」という日本語とは、かなり違う。語源的には、 individual の in は 「否定」 で divide は 「分割する」ですから、これ以上分割できない最小単位なのですが、日本では「世間」が一つの単位になっている。 日本語ではどちら かといえばネガティブな意味で言うんですよ。「あいつは個人主義的なやつだ」とか、 そういう言い方をするわけです。ところが、インディビジュアルというのは意味が全 然違っていてもっとポジティブです。
引用元:同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか (講談社現代新書) p.42
結局、「個人」が集まって「社会」ができるわけですね。先ほど少し触れたように、もともと日本にあったのは「世間」ですけれども、明治時代に「個人」と「社会」と いう言葉が入ってくるわけです。インディビジュアルとソサエティが入ってきて、そ れを翻訳したわけですね。この時に、近代市民社会という概念が輸入されたのですが、 基本的に個人がいない 「世間」みたいな関係、今、僕たちが持っている人間関係と同 じようなものは、昔は世界中のどこにでもあったと思うんです。ただ、特にヨーロッパの場合は、一二世紀ルネサンスなどと言われるように、今から八〇〇年、九〇〇年前に、インディビジュアルが形成され社会ができてくるんですね。この頃、ヨーロッ バの中心部には、都市が成立し、新しい人間関係が生まれてきます。
「個人」が「社会」をつくるヨーロッパと、「世間」が「社会」をつくっているようにみえる日本。
そんな日本に住んでいると一個の人間に「個人」の不在を疑問に思う機会は、さほど多くはありません。
けれどひとたび「世間」の居心地の悪さや、常識とされることの論理性の破綻に気が付くと、堰を切ったように「個人」でいることの重要性を身に染みて分かるようになるのです。
「世間」的思考を排した僕の5年間
「ありきたり」なデザインのほうが難しい?
ここからは僕の経験談。
僕は20代の前半頃より、デザイン業界で仕事をしていました。
この業界には「デザイン事務所」と名のつく事業所は、数えきれないほど存在するかと思います。
僕がはじめて足を踏み入れた会社は、神奈川県の外れにある、小さなデザイン事務所でした。
そこではとことん「世間」の考えを否定することからはじまったのです。
「常識」「当たり前」「普通は」といった決まり文句を、思考の中からなるべく排除していく。
デザイン業という手前、アイディアや発想力が必要な特殊な業態ゆえに、誰かと同じ考えをすることは他の同業他社と競争にならないのです。
いや、これには語弊があります。
誰でも考え付くアイディアを持ちながら仕事をこなすことは間違いではないし、可能です。
むしろ「ありきたり」な制作物は、誰がどう見ても「パチンコ屋の看板だ」「スーパーの広告だ」と瞬時に理解してもらえる。
実はルーティンの業務の中では、想像力を働かせて物事に取り組む機会はさほど多くは無いのです。
そうした意味では「ありきたり」な制作物を完成させることの方が、「常識」を理解していないと難しいのかもしれません。
ただし、普段から「世間」の「常識」のようなものに捉われていると、発想力が求められるシチュエーションに遭遇しても対応できません。
例えば、「パチンコ屋の看板を作ってほしいんだけど、ウチと瞬時にわかってもらえるようなデザインにしてほしい」という案件。
パチンコ屋であるという体裁を保ったまま、そのお店なりの独自の「色」を出していかなければならない。
このように「ルール」や「常識」といった枠は存在するものの、その範囲を超えない形でオリジナリティを付加しなければならない…。
実は、デザイン事務所では、そんな業務がほとんどなのです。
ゆえに「常識」と「非常識」のあいだを行き来できるような思考が求められるのです。
単純な論調だけでしか、物事を捉えられない「世間」の大人
当時の社長には「なんで普通は〇〇なんだと思う?」など、あらゆる場面で問われました。
「普通」を重んじる家庭で育ってきた僕には、返答に窮するばかりで、「そういうものだから、そうでしょ!」と考えることを辞めてしまうのです。
そんな僕に対して、社長は延々と物事の成り立ちや考え方を一緒に探ってくれたのは、いまの僕の大きな糧になっています。
振り返ればそれは、「世間」という檻から外に逃げ出す訓練でもあったのだと思うのです。
以降、どれほど多くの事柄が「世間」が醸し出す「普通」や「常識」といった空気感によって構成されているのかを思い知ったのです。
テレビを観れば「世間の常識」を流布することに必死で、ご近所の「世間話」は現状のコミュニティを変えまいとすることに苦心している…など。
今まで素通りしてきたものの何もかもが実は、考えてみればオカシイことばかり。
だからこそ、ウクライナの状況を一方向のみでしか見られていない意見に恐怖感を抱くし、僕よりもずっと年上の人間が、そんな浅い認識を、あたかも正論のように周囲に吹聴することが大いに落胆するのです…。
〈世間ー間ー存在〉という思考
そうした体験もこの本では、以下のように捉えられています。
佐藤 で、どうしたらいいのか。『なぜ日本人はとりあえず謝るのか』(PHP新書)に 書いたことがあるんですが、「世界内存在」というハイデッガー (Martin Heidegger) の言葉を借用して、〈世間ー内ー存在〉〈世間ー外ー存在〉 〈世間ー間ー存在〉という三つの生き方があるのではないかと考えました。〈世間ー内ー存在〉はふつうのあり方で、僕たちはどこかの「世間」に属していて、 そこから排除されると〈世間ー外ー存在〉となる。それはひょっとすると、「社会」というもののなかに放り出された存在となってキツイ。だけど、〈世間ー間ー存在〉という、いろんな「世間」の間をとにかく生きる、という生き方ができるのだったら、それが一番いいんじゃないかと考えました。哲学者のドゥルーズ=ガタリ (Gilles Deleuze P.F. Guattari) が、それを「独身者」と呼んでいます。鴻上さんの「ほんの少し賢い個 人」に通じるのではないのかなと。
引用元:同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか (講談社現代新書) p.156
僕がデザイン会社で経験したのは、〈世間ー間ー存在〉という思考法を植えつけられたこと。
そんな考え方をしなくても、ある種の「感性」でデザインを行うことができるのかもしれませんが「感性」の劣った、〈世間ー内ー存在〉思考だけの僕のような人間には、デザイン業は到底不可能。
そんな未熟な僕を的確に捉えて、少しずつ〈世間ー間ー存在〉思考を、社長は植えつけてくれたのだと思うのです。
ここまで偉そうにデザインを語りましたが、ついぞ僕には「デザイン感性」を得ることができませんでした(笑)。
何が足りないかと言えば、先にも書いた通り「常識」と「非常識」を渡り歩くデザインの修練が足りなかった。
つまり、自分と他人の制作物を比較し、次に活かす反復の練習が圧倒的に足りなかったのです。
その代り、デザイン事務所にいながらして文章を書く業務が多くなり、今に至る…。
「適材適所」とはこういうものなのかもしれません。
「世間」を渡り歩くことが大切
本書はコロナ禍のなかで書かれていますが、その内容は今後も至極重要となるでしょう。
世界はウクライナ危機の対応に迫られ、日本はいま(2022年3月)止まることを知らない円安を迎えています。
世の中が今まで以上に生きづらく、居心地が悪くなるのは確実です。
そうしたなかで世間とどう付き合っていくべきか。
佐藤 僕も基本的に鴻上さんが言ったことと同じ思いを持っていますが、おそらく 「世間」というのはこの先もなくならないと考えています。この状況は続くでしょう。 その前提のもとで、「世間」をよく知る。 「世間のルール」とかも含めて、よく見てよ く知るということが非常に大事なことだと思います。知ったうえでどうするかという のは、これは鴻上さんと基本的に一緒です。いろんな「世間」とつながるということ。 〈世間ー間ー存在〉を意識して、少しでも「世間」に風穴をあけてほしい。そうなれ ば、もう少し自由闊達に生きることができるんじゃないかと思います。
引用元:同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか (講談社現代新書) p.170
いつも同じコミュニティだけに属さないで、あらゆる「世間」を渡り歩く。
それは別にリアルな対面ではなくとも、本を読んで見識を広げるとか、そうした身の回りで出来ることからはじめれば良いのかもしれません。
以前、中根千枝さんの書籍を紹介したときにも書きましたが、本書でも同じようなことが書かれていました。
僕らが生きているこの日本。
別に「世間が狭い」のではなくて、きっと「狭い世間しか知らない」のです。
「社会」という集団意識の欠けた日本では世間を意識して、たったひとりの「個人」を深く胸に抱いていけるようになりたいものです。