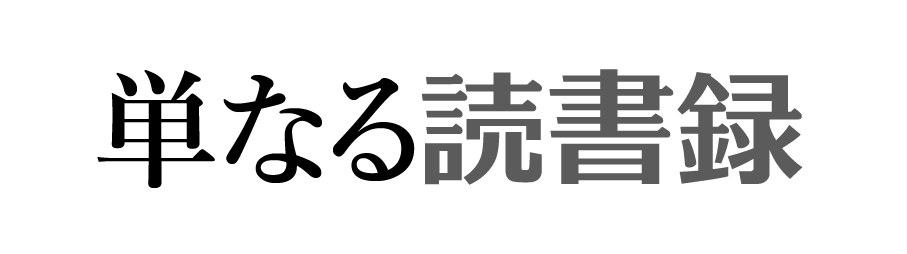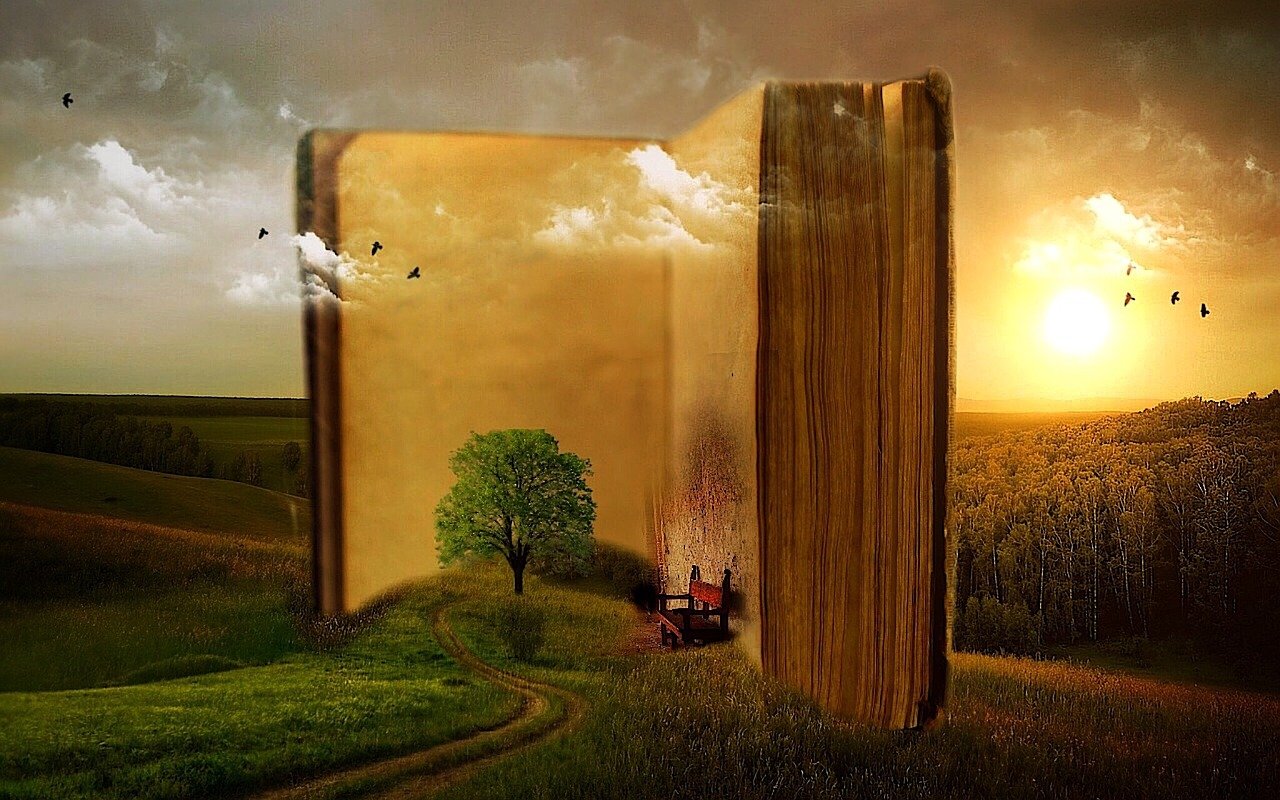最近、ノンフィクションばかり読んでいたので、久しぶりに小説が読みたくなった。
以前から気になっていた小説を買いに書店を巡ったがお目当ての本がなかなか見つからない。
比較的大きな書店にもなかった。
とくにマイナーでもない著者の、人気作家のものだから必ずあると高をくくっていたが、実際には何件もの書店に足を運んで、やっと見つけたのだった…。
その理由はたぶん、探していた本が「単行本」の小説だからだろう。
書店の棚から単行本が姿を消しつつある。
この現象は、出版業界全体の構造的な変化、読者の購買行動の変化、そして書店の経営戦略の変化が複雑に絡み合って生じているらしい。
まず、出版業界の構造的な問題として、「委託販売制度」が挙げられる。
この制度は、書店が売れ残った本を出版社に返品できるというもので、書店の負担を軽減する一方で、出版社は返品リスクを抱えることになる。
そのため、出版社は慎重に重版を決定し、結果として品切れになることがある。
また、出版物の流通を担う取次(問屋)の力が強く、書店の仕入れに影響を与えることもある。
あるいは読者の購買行動の変化として、インターネットやSNSの普及が挙げられる。
読者は書店に行く前に購入する本を決める傾向が強まり、書店の店頭で偶然出会う機会が減っている。
インターネット通販や電子書籍を利用することで、実店舗の在庫状況に左右されずに書籍を購入できるようになったのも、極めて大きな要因だろう。
書籍がなかった場合、書店での取り寄せを待つよりも、配送によってすぐに読めることも極めて大きい。
そして特に大きな要因としては、単行本の価格の高さが挙げられる。
書籍価格の値上がりも他の物品同様に凄まじい上昇をみせている。
これは、書店の経営や読者の購買行動に大きな影響を与えることだろう。
単行本の製造コスト、初版発行部数、情報量などが価格に反映され、読者にとっては購入のハードルが高くなる。
また、文庫本という存在も無視できない。
文庫本は、単行本に比べて価格が安く、普及を促進する役割を担う。
単行本で人気となった作品が、後に文庫本として発売される「文庫落ち」という現象も、読者の購買行動に影響を与える。
すなわち、「文庫落ち」を待つ読者層も少なからず存在するのであり、文庫本が売れてしまう以上、そうした形態でのメディアで発売するほか術がなくなってしまう。
結果として「払った対価」と「読後感」などが、書籍に対して釣り合うかどうか…つまり費用対効果(コストパフォーマンス)がより一層求められるような気がするのだ。
特に小説など、知識よりも物語を消費するうえでは、価値観の変化が消費者に起こってもなんら不思議ではないと僕は考えている。
AIも普及し、手軽に物語を消費するうえで「紙」を媒体とする意味が一層問われるように思う。
これらの要因が複合的に作用し、単行本が書店に置かれにくくなっている。
しかし、単行本には、作家の代表作や人気シリーズ、専門書や学術書、装丁や造本にこだわった書籍など、文庫本にはない魅力がある。
そう、それに誰よりもいち早く読みたい!という欲求もある(笑)。
書店は、単にサイズや価格だけでなく、販売動向、読者のニーズ、書店のコンセプトなどを総合的に考慮して、どのような単行本をどれくらい置くかを決定することがますます求められることになるだろう。
…が、難しい時代だ。
とはいえ、好きな作家の本はなるべく紙の本で手に取り、読みたいと思うのは、今のところ変わりはない。