前回の記事に「僕は小説を読まないことにしている」と書きました。
その理由は必要以上に感情移入してしまって、疲れてしまうから。
ところが、コロナ禍や豪雨の続くお盆休みに小説を読んでも良いだろうと手に取ったのは村田沙耶香さんの「コンビニ人間」。
2016年の芥川賞受賞作です。
あらすじ
「白羽さん」の登場で進む物語
主人公の年齢は36歳女性、独身、アルバイト。
年を重ねるごとに世間から求められる「普通」の基準というか、ハードルが高くなる。
軽々に生きづらい社会だと言ってしまえばそれでおしまいだけれど、読み進めるごとに身近にあるような生きづらさを再認識、共感してしまうのです。
序盤までは読者である僕自身もコンビニで働いているかのような錯覚に陥るほど、コンビニで働く描写が延々と続きます。
中盤、婚活目的でコンビニに職を求める白羽さんが登場すると、少しずつ物語に「色」が加えられていきます。
白羽さんの性格はどこか根性が曲がっている。
何に対してもすぐに文句を言いたがるし、空虚な自信を持ちながら、世間に対して恨みを抱く。
そのくせ仕事ができないし、現実的ではない夢や希望にすがって生きている…。
つまりは社会的な実績を伴わずに、自己承認を得たい欲求のままに生きてきてしまった。
世間で言うのなら「中身のないヤツ」とでも言われてしまうのでしょうか。
そんな白羽さんを冷静に観察する主人公の古倉恵子は、白羽さんがコンビニによって「修復」、すなわち排除されるだろうと予想する。
結果、白羽さんはコンビニ店員という職をクビになる。
そんな白羽さん曰く
「僕はそれで気が付いたんだ。この世界は、縄文時代と変わってないんですよ。 ムラのためにならない人間は削除されていく。狩りをしない男に、子供を産まない女。 現代社会だ、個人主義だといいながら、ムラに所属しようとしない人間は、干渉され、無理強いされ、最終的にはムラから追放されるんだ」
そしてそんな干渉を白羽さんは「強姦」であると表現します。
世間の普通に苛まれる
コンビニに限らず、「職場」というのは世間の構成する一部分であり、我を押し殺して世間に求められる人間性を演じなければならないこともあります。
そんな職場に限りになく適応してしまった主人公の職業は、非正規の、しかも他人から見下されてしまうようなコンビニ店員。
どんなに自分が天職のように思っていたとしても、世間が認めてくれなければなぜか、働き盛りの独身がコンビニのアルバイト店員として働き続けることは許されない。
結婚するか、就職して働くのか。
このどちらかひとつでも達成されなければ、世間は「普通」の30代女性として認識してはくれません。
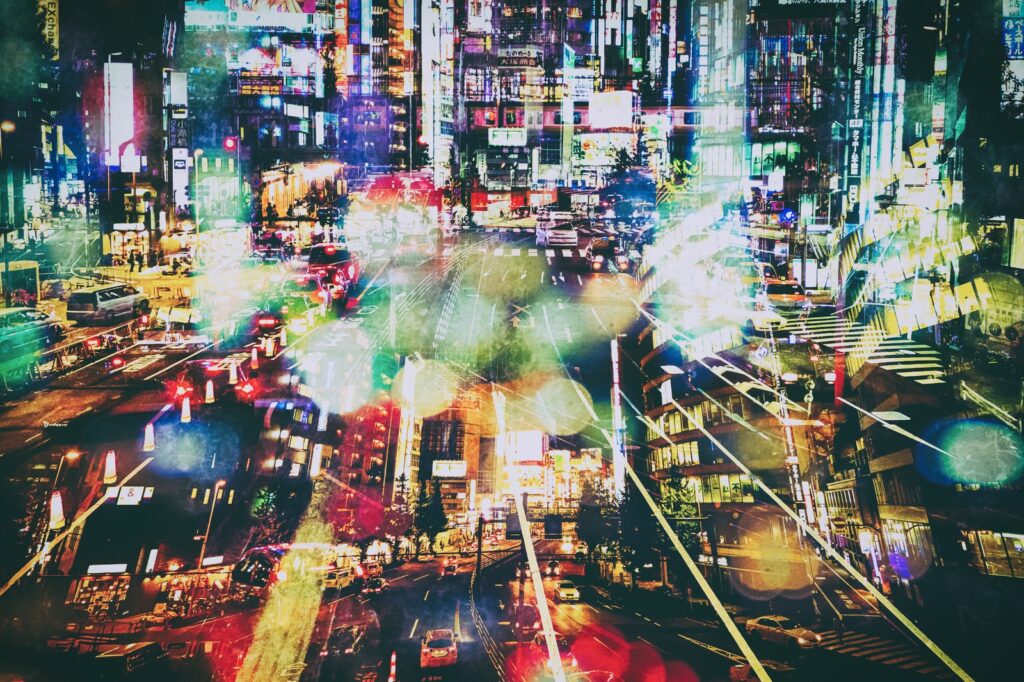
それに適応するためにいくつかの手段を講じようとするのですが、やっぱり立ちはだかるのが縄文時代から変わらないとされる「ムラ社会」的な構造。
「ムラ社会」を構成しているコミュニティに属する人間は、自らを「普通の人間」であると思い込んでいて、それゆえに他者をも「普通の人間」であるように強要する。
主人公と白羽さんが抗っているのは、そんな普通の人間への違和感なのでしょう。
「コンビニ店員」という架空のキャラクターを演じつつも、「普通の人間」として社会の歯車になれる安心感に寄りかかっていた主人公もだんだんと、「ムラ社会」の歪な掟に苛まれていくのです。
感想と考察
仕事ができるひと、できないひと
読了してまず感じたこと。
主人公が「普通」に仕事ができる人で良かったね、と。
何故だろう、嫉妬にも似た感情が湧いてくるのです…。
物語の中で主人公がずば抜けて仕事ができると自己評価している描写はなくとも、恐らく標準以上に仕事ができる人なのでしょう。
だからコンビニ店員として長く勤めることができたのであって、それこそが主人公のアイデンティティを保っていたのだと思うのです。
いっぽう白羽さんは仕事ができない。
いつもどこか上の空で、業務に身が入らない様な描写が散見されます。
そして周囲の人間は仕事ができない男性を
「人生終了だよな。だめだ、ありゃ。社会のお荷物だよ。人間はさー、仕事か、家庭か、どちらかで社会に所属するのが義務なんだよ」
と主人公に語りかけるのです。
世間の「一般常識」においては、仕事か家庭に携わることにのみ社会との係わりが存在せず、それ以外は、社会のお荷物なのだという認識が広く蔓延っているということを示している表現だと思います。
一度その地位から転落した途端、一気に社会のお荷物と認識されてしまうのが現状で、なんとも「普通」が貴重で遠い存在なのでしょう。
白羽さんの深層心理には、どれほどコンビニのような職場で努力しても、認められることはないという思いが働いていて、それは世間の考える「基準」や「尺度」が白羽さんには分かるからこそなのだと感じます。
ところが、主人公にはその「基準」や「尺度」が分からない。
俗にいうところの「空気が読めない」。
この物語の中で主人公と白羽さんはある意味、対になっていて、物語では絶妙なバランスを取り合う。
けれど終盤、主人公にとって「社会との係わり」であるコンビニ店員という職を失いかけたとき、対の関係に終わりがみえる。
主人公はコンビニ店員という生き方を自分なりに咀嚼し、悟りにも似たような思いを抱くのです。
すべてが解決したわけではないけれど、先述の「人間の義務」を主人公が少しばかり理解できた瞬間でもあるように思います。
ところが白羽さんの問題は解決できていない。
実際に白羽さんのように何をやっても仕事ができない人というのはいるもので、努力によって解決しない場合もある。
ほんとうは周囲の人間がそれに気づいてサポートすることも大切なのかもしれませんが、努力主義の社会にあって努力をしていないように見える人にはなかなか理解が及びません。
なぜ、白羽さんに僕は感情移入してしまうのか。
それはきっと僕の性格もどこか白羽さんと共通するものがあるからなのかもしれません。
いや、「自分は仕事ができない」と自己認識をしている人は案外多いはずで、それをも含めて白羽さんというキャラクターを著者は描いたのでしょう。
たまたま仕事ができる人にはやっぱり生きやすい、解決に道のりが見える社会を暗に表現しているように思うのす。
「変」を隠す人、隠さない人
さらに感じたのは、主人公は「変」であることを隠そうとする。
白羽さんは「変」であることが滲み出てしまう。
両者にとって自分が「変」であることが周囲の人間にバレることを恐れているのか、いないのかも注目すべき箇所です。
その点を考えるに、白羽さんは自身が「変」であることを隠す時期をとっくに過ぎてしまって、「変」を隠しきれている主人公の家に「隠れる」ことでさらなるダメージを受け流そうとしている。
これもまた理に適う行為だったのかもしれません。
コミュニティの構成員としてその関係性を維持していくためには、個人の努力によって「変」であることを極力排除すること。
すぐに正常化されてしまうコンビニと同様に、世間という名の「ムラ社会」は異質なものを容易く受け入れることは、なかなか難しい。
けれども僕らの周囲に起こる齟齬や不和はわりと「変なこと」の欠落、いわば他人の「変」を受け入れられなくなっていることに端を発するのではないでしょうか。
このところよく耳にする「不寛容」と同義です。
そして「変」な人は「変を隠す」か「変な身を隠す」ことが最善の策となる。
しかも、急速に変化する社会では、同じく急速に「変」が増殖する。
ある意味、「変」を「変」と割り切ってうまく付き合っていくコミュニティのほうが、変化を受容しやすく、成長著しいようにも思うのです。
急速に変化する「普通」
この物語はハッピーエンドではないし、完結したわけではないと、僕は思います。
もしかしたら「自分は変」と思っていても、それは世間からみれば「普通」であったり、「自分は普通」と思っていても、世間は「変」として認めない場合もザラにあるわけで。
つまり、自分が「普通」と思っていることは、もしかしたら誰かの「普通」ではないことなのかもしれない。
しかも、自分の見知らぬところでその変化は急速に訪れていて…。
一歩立ち止まって、「普通」の棚卸を、ことあるごとに行わなければならないのかもしれません…。




